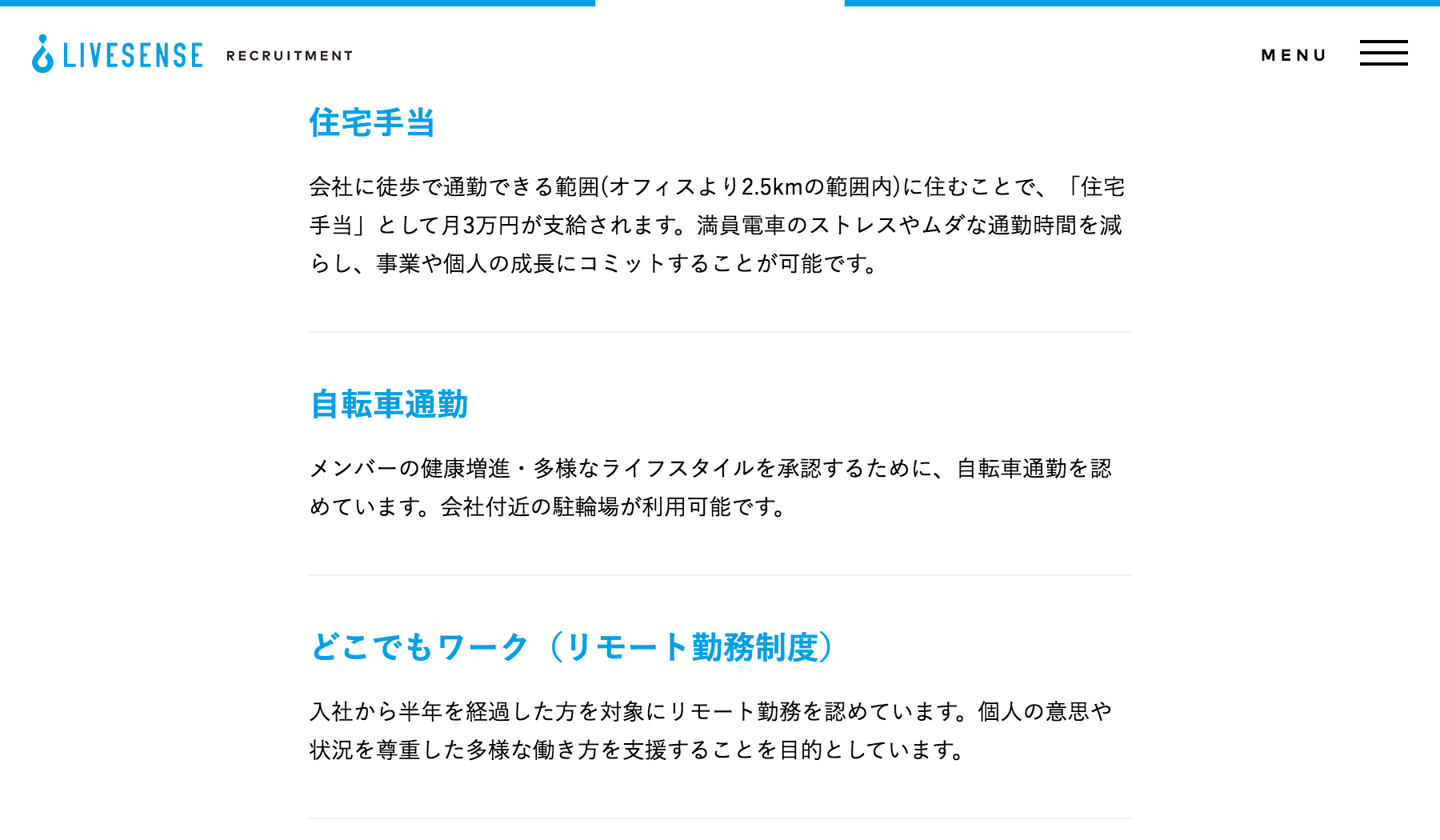企業が交通費を削減する9つの方法を解説

企業のコスト削減施策として有効なのが、「交通費」です。総務や人事担当者は改めて、従業員の交通費を見直すことで、大幅なコストカットを見込めます。
従来は交通費削減の施策は限られていましたが、最近ではITツールの活用によって、自宅での勤務やミーティングをWeb会議で行うことによって、移動にかかる交通費を大幅に削減できるようになりました。
本記事では、交通費削減を模索する総務や人事担当者、また経営者に向けて具体的な交通費削減の方法をご紹介していきます。
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
企業にかかる交通費とは?

交通費とは、従業員がオフィスに出社するまでにかかる公共交通機関の利用費「通勤交通費」を指すことが多くなっています。実は、交通費は法律上支給が義務付けられていません。そのため、通勤のために交通費を支給しなくても、問題はありません。
しかしながら、多くの企業では通勤にかかる交通費を支給しています。従業員が円滑に業務を行うために必要な経費と捉えることが多いためです。
交通費は、通勤定期代の他に以下のような経費を含めます。
- 通勤定期代
- 自社オフィス外でのミーティングや会議場所への移動費
- 終電後の業務や接待後に必要となったタクシー代
- 営業先へ車で移動する際のガソリン代や駐車料金
これらの経費を改めて見直すことによって、コストの削減を可能にします。
企業が交通費を削減する9つの方法と企業事例
ここからは、今から企業が実施できる交通費の削減方法についてご紹介します。
- 通勤定期の長期支給
- 通勤ルートの最適化
- オフィスの近くに住む従業員の家賃を補助
- 自転車通勤や徒歩通勤を推奨する
- 出張時は格安航空(LCC)を利用する
- タクシー利用を制限する
- 社用車のガソリン代を節約
- テレワークを導入する
- Web会議システムを導入する
テレワークの導入やWeb会議システムの導入といった方法は、交通費だけでなく従業員の無駄な業務時間の削減も期待でき、企業の成長そのものをサポートします。
完璧なビデオ、クリアな音声。インスタント共有「Zoomミーティング」

出典:Zoom公式ページ
Zoom ミーティングは、世界各国75万以上の企業や組織で利用されているWeb会議サービスです。
通信速度が比較的低速なネットワーク回線でも途切れにくく、音声の途切れがほとんどありません。
Web会議の開催にライセンスを取得する必要があるのは主催者のみで、参加者は会議アドレスへ招待されることで、ブラウザから誰でもWeb会議へ参加できます。
ブイキューブが提供するZoom ミーティングの有料版では、ミーティングの映像や音声を録画・録音してクラウド保存しておくことが可能です。
投票機能やユーザー管理機能もついており、ビジネスシーンでも快適に利用することができるでしょう。
また、プランに問わずメールでのサポート体制を提供しています。エンタープライズプランでは企業に合わせて導入・運用を支援してくれるなど、利用者に最適なサポートが充実しています。
Zoomの有料版を使うべきメリットとは?
Web会議ツールZoomの有料版を使うべきメリットについては、「Zoomの有料版を使うべきメリットとは?無料プランとの違いや決済方法を解説」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてお読みください。
1.通勤定期の長期支給
企業が従業員の交通費を削減する上で、最も手軽にできる対策が「通勤定期の長期支給」です。電車代やバス代といった公共交通機関の通勤定期は、1ヶ月単位で購入するよりも、3ヶ月や6ヶ月といった長期で購入した方が安い傾向があります。
|
通勤定期の期間(東京〜新宿間) |
金額 |
|
1ヶ月 |
5,930円 |
|
3ヶ月 |
16,900円 |
|
6ヶ月 |
28,460円 |
上記は、東京駅〜新宿駅までJRを利用し通勤定期を購入した時の金額です(2020年2月時点)。1ヶ月単位で購入するよりも、3ヶ月単位・6ヶ月単位で購入する方が、通勤定期代を抑えることができます。
仮に、1ヶ月の通勤定期を6回購入した場合、かかる金額は35,580円です。しかし、6ヶ月の通勤定期だと28,460円になり、7,120円分お得になります。従業員が100人いる場合、70万円以上の交通費削減が可能です。
なお、今回は例として東京駅〜新宿駅の金額を出しましたが、通勤区間が長ければ長いほど、長期で購入した方が安い傾向にあります。
2.通勤ルートの最適化
「通勤ルートの最適化」も見落とされがちな視点です。通勤定期の購入方法は、賃金規定などに明記されているのが一般的です。この際に、自宅からオフィスまでの最安・最短ルートで購入する旨を必ず記載するようにしましょう。
従業員によってはプライベートな理由で、ターミナル駅などを経由してオフィスに向かう通勤定期を購入する場合があります。企業によって規定は様々ですが、交通費削減の観点からみると、最安・最短ルートを推奨しましょう。
3.オフィスの近くに住む従業員の家賃を補助
従業員の自宅からオフィスまでの通勤距離を短くすることで、交通費を安くできます。例えば、オフィスから2km圏内に住む従業員に対して、家賃の一部を補助することで、通勤定期の購入金額を抑えることが可能です。
最近ではIT関連企業を中心に、このような家賃補助制度を導入する企業が増えています。これらの制度は、交通費削減という観点だけでなく、満員電車や長時間通勤というシチュエーションをなくすことによって、社員の心身の安定をサポートするという意味合いもあります。
オフィスの近くに住居を構えることによって、交通費を削減できるだけでなく通勤ストレスを取り除き、業務に集中してもらうことができます。企業の生産性向上も期待できる施策と言えるでしょう。
企業事例|株式会社 サイバーエージェント「2駅ルール」
ゲーム事業やメディア事業・インターネット広告事業を手がける株式会社サイバーエージェントは、福利厚生制度の1つとして、「2駅ルール」を採用しています。
勤務しているオフィスの最寄り駅から、各線2駅以内に住んでいる社員に対して、月3万円の家賃補助を支給しています。
4.自転車通勤や徒歩通勤を推奨する
上記でご紹介した家賃補助制度と似た制度ですが、バスや電車といった公共交通機関を利用せずに、従業員に自転車や徒歩で通勤してもらうことによって、交通費を削減できます。
「健康経営」というキーワードが話題になっている通り、企業が従業員の体調を管理することで活力や生産性を高めようという取り組みが進んでいます。従業員が健康を損ねると、業務がストップしてしまい、企業成長の妨げになります。
自転車通勤や徒歩通勤は、交通費を削減するだけでなく、適度な運動を従業員に習慣化させることで健康維持の効果を期待できます。ただし、自転車通勤の場合、オフィスに駐輪場の整備するもしくは近隣の駐輪場の利用料金をサポートするなどの仕組みづくりが必要です。
企業事例|株式会社LIVESENSE「自転車通勤手当」
出典:制度・環境・文化について | 株式会社リブセンス | 採用情報
「あたりまえを、発明しよう。」をコーポレート事業に掲げ、インターネットメディア運営事業を中心に行う株式会社リブセンス。従業員の健康増進と多様なライフスタイルを承認するために自転車通勤を制度として採用しています。
また合わせて「住宅手当」も福利厚生制度に用意。会社に徒歩で勤務できる距離(オフィスより2.5km圏内)に住むことで、月3万円が支給されます。
5.出張時は格安航空(LCC)を利用する
交通費として企業の負担になっているのが、出張をする際の移動にかかるコストです。企業によっては、国内だけでなく海外への出張が頻繁にある会社も多いでしょう。
その際に、見直したいのが「航空券」の価格です。LCC(格安航空会社)を利用することで、出張費を抑えることが可能です。ただし、航空会社によっては、欠航時の保証が受けられないケースや早期でチケットを購入する必要があります。急な出張などにはLCCでは対応できない可能性もありますので、柔軟にルールを決めておく必要があるでしょう。
6.タクシー利用を制限する
接待時や残業時にタクシーを利用する従業員も多いのではないでしょうか。会社の業務遂行上に必要だった場合、タクシー料金は企業が負担するのが一般的です。
しかしながら、実際にタクシー利用の実態をみると、必ずしもタクシーに乗る必要がないのにも関わらず、利用される場合があります。そのため、タクシー利用に関しては社内で明確なルールを設ける必要があるでしょう。
例えば、接待後でも電車やバスといった公共交通機関を利用できる場合は、タクシーの利用を原則的に禁止するといったものです。また部署やチームごとに月内のタクシー利用の上限を定めるといったルールを設けている企業もあります。
7.社用車のガソリン代を節約する
営業車など社用車を頻繁に利用する会社では、ガソリン代を節約するのも交通費削減の手段の一つです。
例えば、大手のガソリンスタンドには、「ガソリン法人カード」と呼ばれる専用のクレジットカードがあります。社用車が複数台ある場合は、このカードを利用することで、給油にかかるコストの削減ができます。
8.テレワークを導入する
ICT技術を活用することで、オフィスへの出社を必要とせず、自宅や自宅付近のコワーキングスペースやカフェ・サテライトオフィスでの勤務を認める「テレワーク」を社内制度として導入するのも、交通費削減に効果的です。
通勤にかかる交通費を削減できるというメリットの他、通勤ストレスがないため、従業員の職場環境への満足度を向上できます。
またテレワークは、育児や介護で出社ができない従業員の離職を防ぐことが可能。新たに採用活動を行う必要がないので、採用コスト削減にも寄与します。
最近では、災害時や新型コロナウイルスの広がりといった緊急時にも、テレワークを導入することによって、事業を継続できるといった点も注目されています。
9.Web会議システムを導入する
遠隔にいる相手と映像や音声でコミュニケーションを取る「Web会議システム」。従来は、打ち合わせのためにクライアントのオフィスや会議室まで移動する必要があり、その度に交通費がかかっていました。
しかし、Web会議システムを導入することによって、自社オフィスにいながら、クライアントとのミーティングや会議を実施できます。交通費に加えて、移動にかかる時間も削減できるので、企業の生産性アップにも貢献するでしょう。
12年連続シェアNo.1の実績を誇るWeb会議システム「V-CUBE ミーティング」は、HD対応の映像と高い接続性で、安定で円滑ができます。対面での会議と同等のレベルと言えるでしょう。
シンプルなインターフェイスで誰でも簡単に扱える他、最大で50人参加できるので、大規模な会議にも対応しています。
まとめ|社内制度を見直して、交通費の大幅削減を実現しよう!
ここまで、交通費の削減を期待できる施策を9つご紹介しました。交通費は、従業員一人ひとりで見れば、そこまで大きな額にはなりません。しかし、従業員が増えると、総額では数百万〜数千万といった額になります。
交通費をゼロにすることはできませんが、1割でもカットができれば、企業の経営には大きな影響を与えます。改めて自社の交通費や移動に関する制度を見直し、より効率的な会社経営へと繋げましょう。