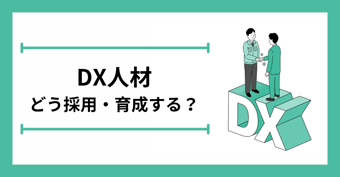企業がデジタル化を進める必要性とは?DXとの違いや導入までの流れ、具体策などを解説
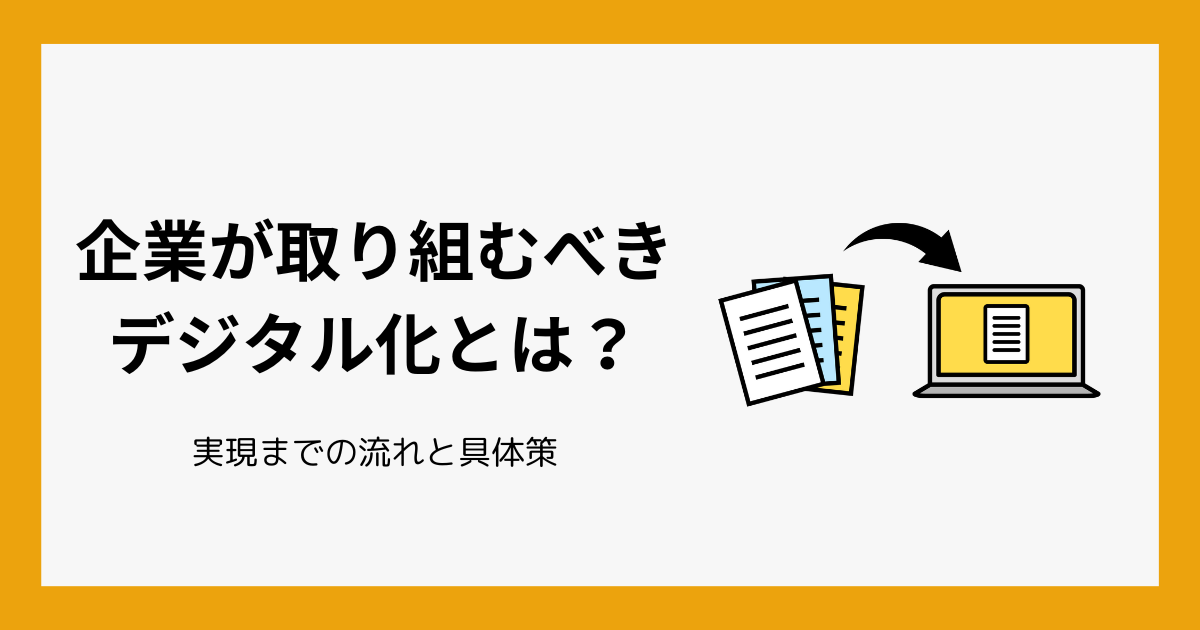
ペーパーレス化やテレワーク導入などのビジネスの「デジタル化」は、競争力を高めるための常識のように扱われています。その反面、総務省の令和3年版情報白書では、「我が国では、デジタル化の基盤となる光ファイバ等ブロードバンドの整備は大きく進展している一方で、そのようなデジタル基盤を用いたICT利活用やデータ活用はまだ十分に進んでいない状況にある」と述べられています。
企業がスムーズにデジタル化ができていない状況といえるでしょう。実際、社内のデジタル化によって生産性向上やコストカットなどを目指したいものの、何から手を付けてよいかわからない企業もあるかもしれません。
そこで今回は、デジタル化とはどういう意味か、必要性・メリット、計画~実行~評価の流れ、取り組み例など、デジタル化に必要な知識について解説します。自社施策にお役立てください。
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
デジタル化とは
デジタル化とは、アナログ・物理データをデジタルデータに移行することです。英語のDigitizationからデジタイゼーションとも呼ばれます。例えば、紙の文書や資料を電子化してペーパーレス化することは、デジタル化の一つです。
また、個別の業務や製造プロセスなどをアナログからデジタルにすることも、デジタル化と呼ばれます。これはデジタライゼーション(Digitalization)ともいいます。例えば、対面会議をWeb会議に変えるなどです。この場合、IT技術が用いられることからIT化と呼ばれるケースもよくあります。
デジタル化の必要性
自社の問題として考えてみると、いまひとつデジタル化の必要性を感じられない場合もあるかもしれません。そこで、ここではデジタル化の6つのメリットを紹介します。
DXの実現
デジタル化とDX(デジタルトランスメーション)は異なります。DXとは、デジタル技術を用いて商品やビジネスモデルを変革し、競争上の優位を獲得するための活動です。つまり、デジタル化はDXを実現するための前提条件となります。
経済産業省のDXレポートでは、日本企業がDXに取り組まなければ、国内全体で最大12兆円の経済損失が生じるとした「2025年の崖」の問題が取り上げられ、大きな注目を浴びました。必ずしも「デジタル化→DX」と進める必要はありませんが、多くの企業はバックオフィス業務など取り組みやすい範囲のデジタル化から始めて、DXにつなげています。
業務効率化・生産性向上につながる
データが紙媒体で管理されていると、業務が非効率になりがちです。例えば、受発注や勤怠管理を紙媒体で行っていれば、データ入力や集計などの単純作業に多くの時間がかかります。
しかし、データを電子化すれば、自動的にデータ入力、集計ができるため、業務効率化や生産性向上が図れます。さらにルーティンワークを自動化して本業に集中できるようになれば、より高度な業務、創造的な業務に従事でき、全体の生産性は上がるでしょう。
また、文字データがテキスト化されれば、目的のものを探すときは検索をかけるだけで済みます。紙媒体だと直接一つ一つ探していかなければならず時間がかかるため、デジタル化したほうが作業効率が上がることが期待できます。
コストを削減できる
デジタル化によって、コスト削減も期待できます。先程説明したペーパーレス化などで業務効率化できれば工数カットが可能です。社内でやらなければならない業務のボリュームを減らせられるのであれば必要な人材の数も減り、結果として人件費節約になるでしょう。
また、Web会議を導入すれば、テレワークやハイブリッドワークが可能です。出社人数を減らせることから、支払う通勤手当の減少、オフィスの縮小化による賃料削減になります。総務省「節電対策としてのテレワーク」によると、オフィスの電力消費量は一人当たり約14%の削減が見込める、とされ、光熱費削減にもつながります。
顧客満足度を向上できる
デジタル化を推進すると、新たな商品、ビジネスモデルを創出できる可能性が高まります。
例えば、電子書籍や動画配信サービスのように、デジタル化によって顧客にとって便利な商品・サービスが数多く誕生しています。また、賃貸物件の内見は、従来本人が出向く必要がありましたが、現在一部の業者では、オンライン内見も可能です。物件から遠いところに住んでいる人でも内見できるようになりました。
このように、デジタル化したサービスは顧客にとって便利に使えるものとなっています。自社のサービスをデジタル化することにより、顧客満足度向上を目指せます。
BCP(事業継続計画)を強化できる
デジタル化によって物理的な制約を受けにくくすることで、BCPの強化も図れます。
自社のシステムをデジタル化をしておけば従業員が自宅にいながら業務可能です。そのため、感染症流行や災害の発生によって出社できない状況でも事業を継続できます。
また、重要文書をデジタル化してクラウド上に分散保管しておけば、事業所が水没、焼失したような場合でもデータを復旧可能です。日本は地震、台風など自然災害が多い国です。物理的なデータの紛失や損傷が起きてもバックアップがあると安心でしょう。
多様な働き方の実現につながる
チャットツールやWeb会議などによるデジタル化で、テレワークやハイブリッドワークなど多様な働き方を推進する企業が増えてきました。日本テレワーク協会による令和4年通信利用動向調査によると、平成25年には1割強だったテレワーク導入率は徐々に増えていき、令和元年には3割弱、令和2年には6割弱に急増しています。
テレワークで在宅勤務できるようになれば、育児中、介護中などの人でも休職、離職せずに働き続けられます。また、遠方に住む人やノマドワーカー(オフィス以外で仕事をするフリーランス)なども雇用しやすくなるでしょう。多様な働き方をする人を採用でき、多種多様な人材確保になります。
デジタル化を進めるステップ
デジタル化の重要性は理解しているものの、何から手を付けてよいのかわからない担当者の方もいるでしょう。ここでは、「計画→実行→評価」の3ステップに分けて、デジタル化を進める流れを解説します。
1.計画
まずはどのようにデジタル化を進めていくか計画をたてましょう。
デジタル化の計画プロセスで最初に行うことは、目的の確定です。例えば、コスト削減顧客満足度向上などの目的を決め、それを達成するうえで障害となっているアナログ業務をリストアップしましょう。
続いて、対策の優先順位を付けます。ボトルネックになっている部分はどこか、成果に直結しやすい部分は何かなどを検討して、デジタル化の優先順位を決めていきます。
なお、計画段階で国の補助金制度を利用できないか検討するとよいでしょう。例えば、インボイス対応のためのデジタル化なら、IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠)で最大350万円の補助を受けられます(2023年度の場合)。
2.実行
取り組む内容と優先順位が決まったら、具体策に落とし込みます。
デジタル化のためには、新しくITツールやシステムを導入しなければなりません。どのようなツールにするのか、どこの業者のものを採用するのか、具体的に決めていきましょう。
自社にIT人材がいない場合や、ノウハウを持っていない場合は、外部のIT業者への相談が必要です。その際何を実現したいかを明確に伝えれば、自社に合ったツールの提案や導入・運用サポートが受けられます。
実行の際は、従業員に対する研修や、業務フロー・マニュアルの改訂も行わなければなりません。事前に業務フロー・マニュアルをしっかり準備・周知することにより、実行の際に混乱が起こらないようにできます。
3.評価
施策を実行したら随時成果を測定しましょう。パフォーマンスを図る客観的な指標を決めておくと、改善につなげやすくなります。
例えば、生産性向上が目標なら労働生産性が一般的です。労働生産性は「粗利÷(従業員数 × 1人当たりの年間勤務時間平均)」で計算できます。幅広いITツール導入を支援している「IT導入補助金」の成果報告でも使われている指標であるため、多くの場合に適用できるしょう。
より細かく成果測定をしたい場合は、ツールによって指標が異なります。ペーパーレス化の効果を評価したいなら、紙代や印刷代の削減額を計算してみるとよいでしょう。
企業のデジタル化の取り組み例
デジタル化として一般的なものは、最初の第一歩となりがちなペーパーレス化と、ビジネスのオンライン化に欠かせないコミュニケーションのデジタル化です。それぞれの施策について詳しく説明します。
ペーパーレス化
ペーパーレス化によるデジタル化の取り組み例は以下のようなものがあります。
|
施策例 |
メリット |
|
マニュアルなど紙媒体の書類の電子化 |
|
|
名刺の電子化 |
|
|
電子取引 |
|
|
社内申請ツールの導入 |
|
コミュニケーションのデジタル化
テレワークやオンラインビジネスの普及に伴い、コミュニケーションのデジタル化を積極的に進める企業が増えています。代表的な施策は次のとおりです。
|
施策例 |
メリット |
|
Web会議 |
|
|
ウェビナーツールによるセミナー開催 |
|
|
ビジネスチャットツールによる社内コミュニケーション |
|
まとめ
社内の業務をデジタル化していくと、社員がどこにいても働けるようになったり、コスト削減になったりと、企業側に大きなメリットがあります。テレワークやハイブリッドワークなどで働きたい人も多く、多種多様な人材獲得にもつながるでしょう。
デジタル化のために新しいITツールやシステムを導入するとき、まずはデジタル化によって何を実現したいか明確にして、必要なツールや導入方法を絞り込んでいくとよいでしょう。自社に合ったアプローチを選べれば、生産性向上やコスト削減など、多くのメリットを得られます。