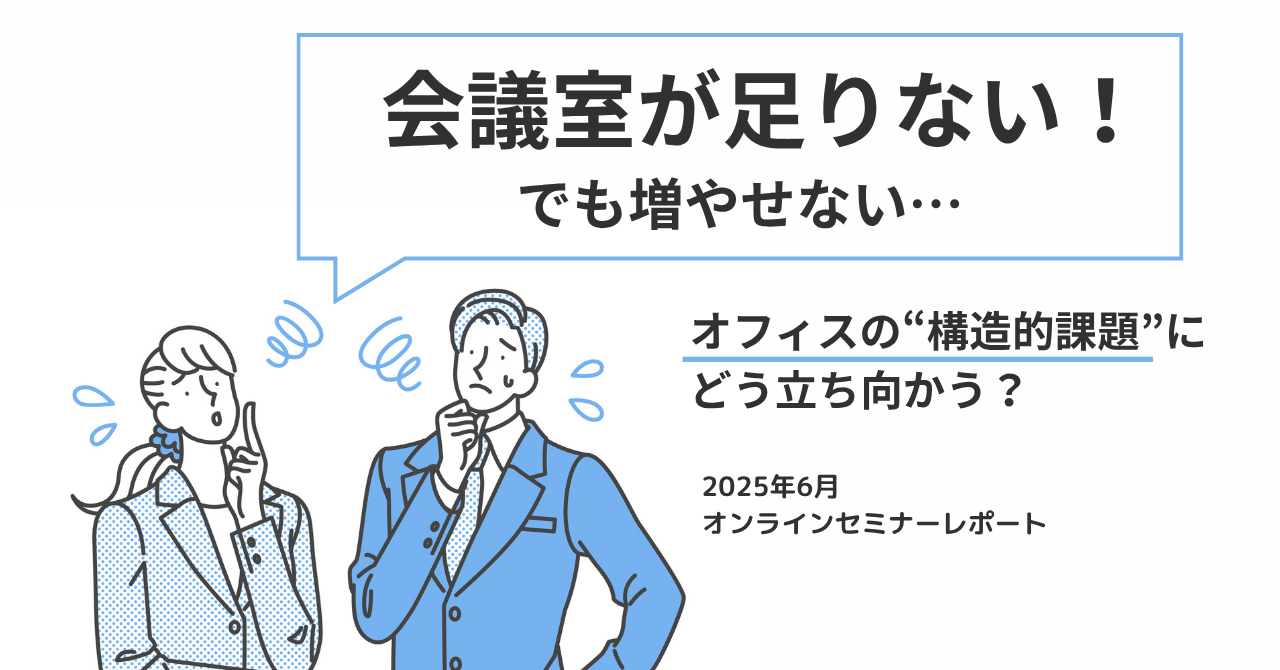
なぜ今オフィス空間の再設計が必要なのか
まず森永氏は、コロナ以降の働き方の変化に対するオフィス環境の“遅れ”について言及しました。
近年、リモートワークの普及により「どこでも働ける時代」が到来し、アクティビティ・ベースド・ワーキング(ABW)という概念が一般化しています。これは、業務内容や時間帯に応じて、働く場所を自ら選べる柔軟な働き方です。
ところが、多くの企業のオフィスは未だに「固定席」や「フル出社」を前提とした構造にとどまっており、そこに矛盾が生じていると森永氏は指摘します。
「静かに話せる場所がない」「Web会議に適した個室が足りない」
実際の現場ではこうした声が多数寄せられているにもかかわらず、オフィス空間はそれに十分応えられていません。
また、会議室の空予約が頻発し、必要なときに会議ができないといった問題も頻出しています。オフィスの利用実態と設計思想がかけ離れているため、空間の“使いにくさ”が常態化しているのです。
「企業は環境に合わせて働き方を変えているのに、空間がその変化に追いついていない」と森永氏は述べ、現代のオフィスに必要なのは“デザイン”ではなく“適応力”であると強調しました。
B工事という「見えない壁」がオフィス改革を阻む
働き方に合わないオフィスを変えたくても、多くの企業が改修に踏み切れない理由。その根本にあるのが「B工事」という大きな壁です。森永氏はこの業界特有の問題を解説しました。
B工事とは、オフィスの内装工事のうちビルの建物側と接続される部分、たとえば空調設備、火災感知器、スプリンクラー、防災システム、電源の配線などを指します。この工事は通常、ビルを建設したA工事の施工業者が指定した業者しか行えません。つまり企業側が「もっと安い業者に頼みたい」と思っても、それは許されていないのです。
森永氏は「この仕組みが、競争原理を働かせない原因です。通常の相場より1.5倍以上の価格になることも少なくありません」と述べ、B工事の非効率性と不透明性を指摘しました。しかもこのB工事は、設計・見積・承認・施工と段階を踏む必要があり、全体の工期の半分を占めることさえあります。
続いて、コストの高騰についても深刻であると森永氏は話します。オフィス改修にかかる費用のうち、B工事は内容によって30〜50%を占めることがあり、さらに建設業界ではコロナ後の資材高騰により、建設コストそのものが全国平均で1.5倍、都心部では2倍以上に上昇しているとされます。

「ABW対応のオフィスに変えたくても、これだけの時間とお金がかかるとなれば、企業が躊躇するのは当然です」と森永氏は語り、既存の制度構造そのものがオフィス改革の足かせになっていると述べました。
“工事不要”で会議室不足を解消する「テレキューブユニット」
前章で、森永氏はB工事の非効率性がオフィス改革の最大の障壁であると語りました。そして、その壁を乗り越える“現実的な解”として提示したのが、「テレキューブユニットシステム」です。

「このテレキューブユニットは、もともとブイキューブが提供していた個室ブースから発展した製品ですが、私たちBDAと連携しながら、今のオフィス課題に真正面から応えるシステムに進化させてきました」と森永氏は紹介しました。
最大の特長はB工事が一切不要であるという点です。ユニットは独立構造であり、ビルの空調や防災設備との接続を必要としないため、従来のようにビル指定業者に高額な工事を依頼する必要がありません。「費用も工期もおおよそ半分で済みます」と強調します。
さらに、設置に際して大規模な解体や内装変更を伴わないため、既存のオフィスの一部だけに導入するといった“部分的な刷新”にも対応できます。「たとえば3ヶ月で導入できる事例もあります。しかも試験導入から始めて、良ければ追加という柔軟なスケールアップも可能です」と語り、段階的な運用が可能である点にも言及しました。
このように、コスト・時間・規制という三重の障害を解消する構造をもつテレキューブユニットシステムを、森永氏は「オフィス空間における現実解」と位置づけ、その導入効果の大きさを参加者に伝えました。
柔軟に変化できる空間こそ、現代オフィスのあるべき姿
森永氏は、テレキューブユニットシステムの優位性はコスト削減や導入スピードだけにとどまらないと強調しました。現代のオフィスにとって最も重要なのは、「状況に応じて形を変えられる柔軟性」だと語ります。
「ユニットは基本的に独立型なので、必要な場所に設置し、不要になれば移設や撤去が可能です。キャスター付きのものであれば、フロア内の移動は社内スタッフでも対応できます」と森永氏は語りました。従来の固定的なオフィス設計では、一度つくってしまえばレイアウト変更には大規模な再工事が必要でした。しかし、ユニット式であれば変化に応じて“動かせる”のです。
さらに、ユニットのサイズバリエーションも進化しています。従来は消防法の制限により、3平米以下の個室しか認められていませんでしたが、最近の法緩和により最大6平米の個室も設置可能となりました。これにより、1人用、2人用、4人用に加え、4〜6人での会議が可能な“2400タイプ”のユニットも登場。「ABWの進化形に対応できる、多用途な個室がようやく現実のものとなった」と森永氏は強調します。

また、BDAではこのユニットを「フレームユニット」と呼ばれる構造材と組み合わせることで、テレキューブ同士の間にセミオープンな共有スペースを設けるレイアウトを提案しています。そこではミーティングや簡易な打ち合わせも可能となり、単なる“箱の集合体”ではなく、全体として「空間をデザインする仕組み」として機能します。
「オフィス空間を一度つくったら終わりではなく、使いながら変化に応じて構成できる。これが、今求められる設計思想です」と森永氏は述べ、テレキューブユニットシステムがまさにその時代の要請に応えるものであると結論づけました。
テレキューブの詳しい製品情報やサイズ・機能比較などを知りたい方は、下記よりテレキューブ製品カタログをご覧ください。
スモールスタートできる“サブスク型オフィス改革”のすすめ
森永氏は、テレキューブユニットシステムのもう一つの大きな特徴として、「サブスクリプション型での導入が可能」である点を挙げました。これにより、初期投資を抑えつつ、運用しながら段階的にスケールアップしていくという、非常に現実的なアプローチがとれるようになります。
「オフィス改革というとどうしても“すべてを一気に変える”というイメージを持たれがちですが、今の時代、それは非常にリスクの高い選択です」と森永氏は語りました。多様化した働き方や個人の価値観に合わせて、空間も柔軟に試行錯誤していくことが求められる今、「最初は1〜2台のテレキューブを試験的に導入し、使用状況や社員の反応を見ながら増設していくのが賢明です」と提案します。
また、サブスクリプション導入であれば、仮に使用状況に合わない場合でも撤去や変更がしやすく、従来の固定的な設計とは異なり、失敗を許容する設計運用が可能になります。
森永氏は、「“空間もサービス化する”という発想が、これからのオフィス改革には不可欠です」と述べ、従来の建築的思考とは一線を画した、柔軟で継続的に最適化される空間の重要性を強調しました。
柔軟な空間戦略が、働き方の進化を支える
現代のオフィスは、急速に多様化する働き方に対して、柔軟に対応できる設計が求められています。会議室不足やWeb会議用スペースの不足といった課題は、従業員のパフォーマンスや業務効率に直結する重要な経営課題です。
森永氏が紹介した「テレキューブユニットシステム」は、B工事という構造的な制約を回避し、スピーディかつ低コストで導入できる実践的な解決策です。特に、サブスクリプション型で小規模から試せるという点は、変化の多いビジネス環境において大きな柔軟性をもたらします。
もはやオフィス空間は、「一度つくれば終わり」のものではありません。事業環境や働き方の変化に応じて常に最適化される“進化する器”として設計されるべきです。そのような空間を持つことが、企業の組織力を高め、持続可能な成長を支える土台となるのです。
さらに詳しい実践方法や導入事例を知りたい方は、「個室ワークブースによるABW実現ガイド」をぜひご活用ください。会議室不足や騒音対策をはじめとした課題への具体的な解決策を一冊にまとめています。

森永 一郎 氏
株式会社BDA 代表取締役社長
1986年武蔵工業大学建築学科卒業
1995年プランテック総合計画事務所入社
2006年株式会社プランテックコンサルティング代表取締役社⻑就任
2009年経済同友会入会
2012年株式会社プランテックアソシエイツ取締役副社⻑就任
2019年株式会社BDA 設立
主な実績として、玉川高島屋SC新南館新築、エイベックス本社改修、IIJ港北データセンター新築、クレディセゾンコールセンター新築、Sony City ( Sony 本社ビル) 新築、スタンレー電気本社新築、武田薬品工業研究所( 湘南Health Innovation Park ) 新築、藤田医科大学キャンパス再編など。
主な受賞歴は、建築業協会賞、BCS賞、JIA優秀建築選、日本免震構造協会賞作品賞、日本建築家協会優秀建築選、グッドデザイン賞、日経ニューオフィス賞など多数アワード受賞。




