リモートワークで支える、働き方の選択〜テレビ会議とチャットで「会う」ことの価値はもっと高くなる

ビジュアルコミュニケーションサービスを提供する株式会社ブイキューブは、ことし創立20周年を迎えます。同社が提供するウェブ会議システムは、様々な企業に導入され、業務の効率化につながっています。近年、日本でも残業の削減や在宅ワークの推進といった、これまでの働き方を変えようという機運が官民ともに高まっています。
今回、同社の創立20周年を記念して、チャットサービスを提供するChatWork(チャットワーク)株式会社(以下、チャットワーク)と対談しました。チャットワークはメールよりも素早く手軽にやりとりが可能なチャットシステムを通じて、スマートな仕事の実現に貢献しています。
両社のサービスの根底には、効率的な業務の進め方の実現と、働く人それぞれが自らを取り巻く環境に適したワークスタイルを実現できることに貢献する、という共通した考え方があります。
今回、両社に対談をしていただきました。テーマは、リモートワークの導入を可能にする会社マインドの醸成方法や、働き方改革への考え方と多岐に渡ります。2人の対談が、働き方に悩む会社員の方々のヒントになればと思います。
※この対談は2018年4月に行われたものです。
なお、対談した2名の役職は対談当時のものです。
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
メールとチャットの違いは、即時性

ChatWork株式会社 CEO 山本 敏行(やまもと・としゆき)
1979年、大阪府生まれ。2000年7月、米・ロサンゼルスに留学中に創業。
2011年にクラウドベースのチャットツール「チャットワーク」をリリース。12年社名を「ChatWork」に変更し、米国法人をシリコンバレーに設立。チャットサービスは、18万5,000社以上(2018年7月末日時点)が導入している。 https://go.chatwork.com/
本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。早速ですが、メールとチャットの違いを改めてご説明いただけますでしょうか。
メールは迷惑メールに代表されますが、様々なメールが同じメールボックスに納められてしまい、メールを探すことに結構手間がかかると思います。
それがチャットですと、一つのタイムラインでまとまりますので、タイムラインをさかのぼれば時系列で内容を追いやすく、途中から加わった人でも、それまでのやりとりを追うのが簡単です。
やりとりのスピードがメールよりも格段に早くなりますね、ほんとに。私も最近、メールを使うことが減りました。
チャットは即時性が大きな特徴で、私は受け取ればすぐに開きますが、メールだといつ開くか分かりません。メールを見てないから、送り主から「メール見ましたか」という電話をもらうという不思議な状況になることもあります。
Web会議システムの開発は、自分が使いたかったから

株式会社ブイキューブ 代表取締役社長 間下 直晃(ました・なおあき):1977年、東京生まれ。1998年、慶応義塾大学在学中に前身の会社を設立。2002年慶応義塾大学院理工学研究科 修了
1998年10月、大学在学中にブイキューブの前身の会社を創業。情報通信技術を高度に活用することで、テレビ電話でもタイムラグのないシームレスな会話のやりとりを実現するサービスを提供している。2006年、社名を現在のブイキューブに変更。企業のみならず、自治体も含めて6,000社以上にシステムが導入されている。https://jp.vcube.com/
ありがとうございます。間下さんがWeb会議システムを導入し始めたときの状況を聞かせて下さい。
アメリカのシリコンバレーにオフィスを開設して、Webサイトや携帯電話向けのアプリの開発をしていた時に、コミュニケーションの壁にぶつかりました。そこで、映像でやり取りができるテレビ会議のシステムを導入しようと考えましたが、1千万円以上と高額で、手が出ないから「自分たちで作っちゃおう」となったのが、きっかけです。
自分たちが使いたくて開発を始めてユーザーも自分たちなので、改善を重ねると半年ぐらいで使い勝手がものすごくよくなって、他の企業にもニーズがあるのではないか、と考えてリリースをしました。
自社製品を自分たちが使うのは、全社員が細かい部分にまでチェックしているので、いいサービスができあがります、絶対。ただ、ビデオ会議の導入が早いですね。今でこそ一般的になってきていますけど、04年だったら相手方に受け入れてもらえないと思います。
確かにそうでした。取引先も導入するためのコストがかかりましたし、何より通信回線インフラがまだまだでした。
今はスマートフォンとタブレットがこれだけ普及して、スマホにもタブレットにも我々が必要とするカメラと画面があるので、どこにいてもウェブ会議もチャットもできますね。
「会う」を補完するためのテレビ会議とチャット

メールやテレビ会議で仕事を進めるという点は、昨今の働き方改革という言葉が出る前に、両社では体現されていたと思います。日本企業では、まだまだ「会えるなら会おうよ」という意識が根強く残っているかと思いますが、それぞれの考えを聞かせてもらえますでしょうか。
私も会うのを避けているわけではなくて、お客さまや取引先と会えるなら会ったほうがいいと思っています。ただ、それを最優先にしすぎるがために、場所や時間をはじめとして様々な制限や縛りを受け入れざるを得なくなると思います。
なので、会うと会わないとを使い分けることが大事です。この使い分けができると、働き方を選ぶことにつながると思います。働き方にあまりにも自由がないのが日本で、それが、最近、ようやく疑問視されてきていますよね。
私も同じように考えています。そのバランスが非常に大事です。弊社もリモートワークがしやすい会社ですが、出社を推奨しています。完全なリモートワークはエンジニアの一部などに現状では限られています。リモートだけだとプロジェクトの進め方で、社員間の温度感がつかみにくいということがありますね。
現状では会うに勝るコミュニケーション手段はなく、「会う」を補完するテレビ会議やチャットを組み合わせることで働き方の自由度を上げる、というのが大事だと思います。
実験的にでも、リモートワークの導入を
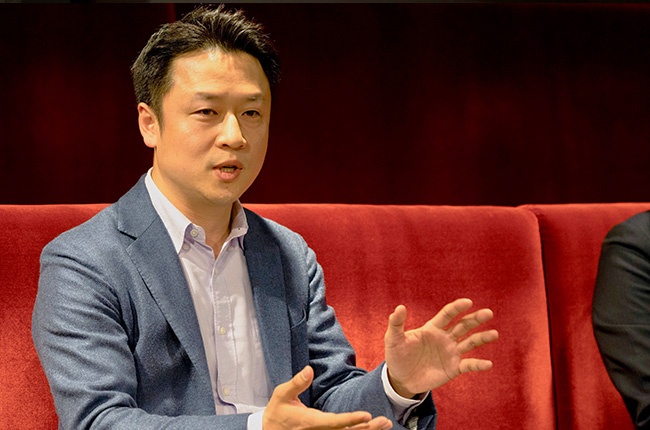
これまでの話で、業務をリモートワークできるか、できないかを見極めるとおっしゃっていましたが、多くの企業はその見極めを難しく感じていると思います。組織作りやルール作りで工夫されているところはございますか。
最近、副業や在宅ワークを認める企業が増えてきていますが、組織ってすぐに変わることができないと思います。ですので、今後はこうした方針で進めていく、ということを組織のトップがメッセージを発して、一歩ずつステップアップしていくことが大切だと思っています。
私たちも昨年10月から本格的にテレワークを進めていますが、それまでは週1回しか認めていませんでした。ただ、少しずつでもやってみないと分からないことってあると思います。実験的な取り組みとして週1回のテレワークを始めて、テレワークでも成果を出すにはどんな工夫が必要で、評価制度をどう変えればいいのか、と会社側も変わらないといけません。
日本の会社はまだまだ年功序列や労働時間で評価が決まるという文化が残るわけですが、ここは根本的に変わらないと働き方の自由度は得られないと思います。週1回のテレワークを行う中での評価制度ができてしまえば、十分に組織は回っていきます。
新入社員は缶詰で、働き方を身に着けさせる

新入社員への教育や研修はどのようにされていますか。
新入社員への研修は、むしろ缶詰でやっています。会社の会議室を借り切って、2~3週間ずっと缶詰でやっています。彼らにはテレワークは適用されません。入社後、業務内容や役割を理解した上で、働き方のベースができればテレワークをしてくれればいいと思っています。
私も同じ考えです。始めに仕事の進め方のベースを徹底的に作った上で、テレワークに移行するのが大切で、自由な働き方を選ぶことは、働き方を身に着けている人しかできないと思います。そうでない人に、自由に働いていいよ、と言ってもどうしたらいいか分からなくなると思います。身に着くまでは、やるべきことを決めてあげた方がいいと思います。 年齢を重ねるにつれて、家族ができるといったそれぞれのライフステージになると思いますので、それぞれの状況の中で働き方を選べるようになるのはありだと思います。
豊かな生活と社会環境を考えると、働き方を選ぶことは必須になるでしょう。
会社トップがテレワークしないと、下はできない

テレワークは、働き方の基盤ができている人でないと難しいと、おっしゃっていましたが、そうすると40代後半や50代のベテランの方々にこそ向いている働き方ではないでしょうか。
50代でも60代でもスマートフォンでLINEをつかいこなしている人もいて、チャット自体にも慣れている方が多いと思います。たとえば部長といった上の立場の人が、ずっとオフィスにいたら下も出社せざるを得ない。上から形を作っていかないと、変わらないです。 セミナーなどで会社経営者の方々には、「あなた自身がテレワークをしてください」と申し上げています。トップならば、時間も場所もコントロールしやすいはずですから。
山本さんはそのあたりは率先していますか。
やり過ぎている感じはありますね。昨年7月まで5年間シリコンバレーにいたので、3か月に1回、2週間ほど帰国するというスタイルでした。
必然性が出てくると、解決策を考えなくてはならなくなるので、トップには率先してリモートワークをやっていただきたいですね
やればいろいろ分かってきますからね。
働き方改革をしないと人を採用できない状況
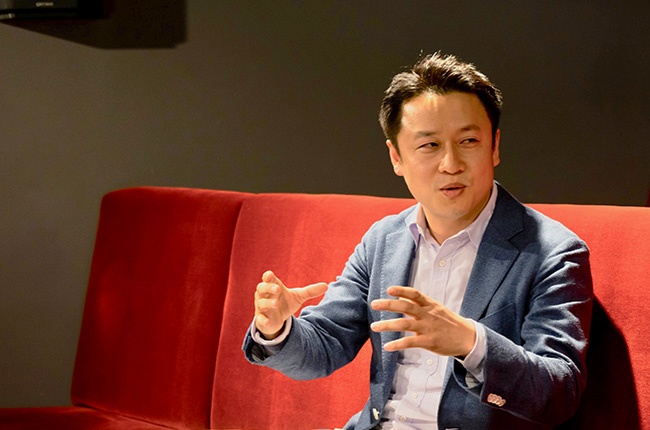
必然性は、お二人の起業のストーリーにも重なってきますね。今回のテーマでもありますが、働き改革を取り入れるようとしている企業は、どうすればスムーズに在宅ワークなどの制度を構築できるでしょうか。
導入当初からスムーズに行くように設計しても結局できないと思うので、組織のキーマンがまずは実践してみることです。実践したら意外とすんなりと組織が回っていくことが分かったというケースが多いと思います。「私の会社では導入は難しいです」と言っていても何も変わらないので、トライをすることが大事ですね。現在の風潮として、取り組まないといけない雰囲気になっていると思います。
その背景のひとつに、人材採用の側面が大きいです。最近の新卒採用では、志望者から「御社の働き方がどうなっていますか」という質問を受けます。人がいないと会社が続きませんから、経営者の切実な悩みはどうやって優秀な人材を確保するか、という視点になってきます。個人個人の事情をうまく取り込んだ働き方にしないと、採用ができなくなってしまいますね。企業としても考えざるを得ないのではないでしょうか。
導入したのはいいけれど、制度だけあって誰も利用していないというのは避けなければなりません。たとえば「失敗してもいいから、利用してみなよ」というトップからのバックアップが必要だと思います。その上で、うまくいった経験は全社に落とし込んでいくというやり方もありだと思います。
変えるのは少しずつ、そうでないと歪みが出てしまう

最後にお聞きしたいのですが、お二人は海外から日本を見ていらっしゃるという共通項もあります。これから日本人が目指していく働き方改革のあり方をどのように考えてらっしゃいますか。
私は様々な場面で言っていますが、日本はとても難しいことをしているな、と感じています。ここ数年で、副業解禁や長時間労働の撲滅、さらには賃上げ、女性管理職30%以上という目標を掲げつつ、雇用は守ります、休日は減らしません、というスタンスはいずれ破綻すると思っています。私が長年過ごしたシリコンバレーとは違い、日本は雇用を守ることが前提なので、少しずつ変えていかないと歪みが生まれてしまうと思います。
働くことは、1日の中で大きなウエイトを占めていると思います。8時間働き、8時間寝たら、残りは8時間しかない。なので、その働く8時間の質を上げないと、人生は豊かにならないはずです。働き方を自分で選んでいいということに気づいてほしいと思います。会社が決めたことに従うのが最優先ではなくて、選ぶようになれることが大事だと思います。
選ぶことは難しいことでもあって、選べない人も出てきます。なので、少しずつやっていけばいいと思います。選べない人はそのままでもいいので、選ぶ人も出てきたということを、周りの人が理解をしていければ、時代は変わっていくと思います。
本日は、ありがとうございました。





