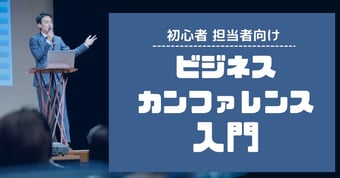カスタマー・エクスペリエンス好事例7選!デジタル×サービスの最新トレンド

2000年頃までの日本では、人々の消費行動の主導権は企業側が握っていました。
総務省の「情報通信白書(令和元年版)」によると、当時のインターネット利用率は40%未満とまだ低く、消費者が商品やサービスを知る手段はテレビCMや街中の巨大広告といったマスメディアに限られていたからです。
しかし、インターネット利用率が80%程度まで上昇し、スマートフォンも普及し始めた2010年以降は、SNSを中心とした口コミやインフルエンサーによる一声が影響力を持つようになりました。
Glossom株式会社が行った「ソーシャルコマースに関する定点調査」では、情報源が購買プロセスに与える影響を具体的に数値化しています。それによると、認知を1とした場合、その後の購入を後押しする力はテレビが0.36、SNSは0.65と、SNSの方が強い結果となっています。
さらに、大量の情報を得られるようになった消費者は、簡単に購入するものを比較検討できるようになり、需要も多様化しました。このように、消費行動の主導権が顧客側へとシフトし、企業がより顧客視点でのマーケティングを必要とする中、カスタマー・エクスペリエンス(CX)という考え方の広まりが勢いを増しています。
カスタマー・エクスペリエンスとは、商品やサービスを利用するプロセスにおける顧客の体験を指します。
カスタマー・エクスペリエンスの向上は、消費者が商品・サービスをリピート購入してくれたり、良い口コミをしてくれたりする可能性を上げることがメリットです。これにより、他社との差別化も実現しやすくなるでしょう。
とはいえ、中にはカスタマー・エクスペリエンスを向上させるためのアイデアを出すことに悩んでいる担当者の方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、進化の著しいデジタル分野を中心にカスタマー・エクスペリエンス向上の成功事例を複数紹介します。各企業のカスタマー・エクスペリエンスに対する姿勢や向上による成果も詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
どこでもドアでニトリへ|株式会社ニトリ
「お、ねだん以上。」をキャッチコピーに家具やインテリア用品を販売する株式会社ニトリ。コロナ禍の2021年2月期、2022年2月期の決算で、売上高・営業利益・経常利益の全てが前年同期比を上回る好調ぶりを見せている企業です。
株式会社エモーションテックによるNPS®調査でも家具業界ランキングで1位を獲得しており、特にカスタマー・エクスペリエンスにおける「商品を探す段階」と「商品を決める段階」に強みがあります。
ニトリはカスタマー・エクスペリエンスの向上について、商品の売れ行き、顧客特性、需要予測などのデータ分析は基本としながらも、顧客とのやり取りという経験も大切にしている点が特徴です。実際、データ的には成功しそうでも、顧客や販売スタッフにフィットしなさそうな施策は採用しないこともあるそうです。
ニトリは2021年8月、「バーチャルショールーム」を開設し、新たなカスタマー・エクスペリエンスの創造に挑戦しています。
自宅にいながらニトリの店舗で買い物をしているような体験ができるバーチャルショールームでは、商品に近づいてサイズを測ったり、気に入った商品をそのまま購入したりできます。
そのため、店舗が近くにない人にもニトリでの買い物を楽しんでもらえます。
また、バーチャルショールームではコーディネートされた店内を見ることで偶然の発見ができることもあります。例えば、ローテーブルを探している人がバーチャルショールームを訪れることで、ローテーブルの下に敷いてあるラグを発見し、「あ、これもいいな」と思う店舗のような体験が可能です。
コーディネートをイメージした結果、購買意欲が高まりセット購入が発生したり、次に買いたいものができることでリピート率の向上につながるでしょう。
※参考:まるでどこでもドア!?家にいながらニトリに来店できる、バーチャルショールーム
NPSでファンが急増|東京ヤクルトスワローズ
株式会社ヤクルト球団が東京を本拠地に運営する東京ヤクルトスワローズは、NPS®を活用してカスタマー・エクスペリエンスを大きく改善した事例を持ちます。
NPS®とは「Net Promoter Score(ネット プロモーター スコア)」の略で、顧客ロイヤルティの程度を数値化する指標のことです。これまで明確にするのが難しかった顧客の感情面を数値により分析できるため、カスタマー・エクスペリエンスの具体的に改善することに役立てられています。
ヤクルトスワローズは、ファンクラブの会員数増加と黒字収益化を目指してはいたものの、他球団と比較してファンクラブが小規模にとどまっていました。
会員を対象としたアンケートを実施しても、質問が漠然としていたり、ファンの声を拾いきれなかったりしていたため、あるべき姿に対して適切な施策を打てていなかったそうです。
そこで、NPS®を活用し具体的なデータを分析したところ、地方のファンも大切にしてほしい、選手との距離感が近いのはいいがイベントが少ない、といった声が多いことが判明しました。
球団としては、地方のファンも大切にしているし、イベントも足りているという認識だったため、結果に対する驚きは大きかったといいます。NPS®では、こうした認識の誤差を明らかにできるのもメリットです。
その後ヤクルトスワローズは、地方での試合の際にピンバッジやご当地ロゴを入れたユニフォームを配布したり、選手と触れ合えるイベントを増やしたりする施策を実現しました。
その結果、カスタマー・エクスペリエンスが改善され、ファンクラブの会員数が前年比110%を超える数値で推移を継続。6つある会員ランクのアップグレードも毎年数千人規模で起こるようになったそうです。
※参考:Swallows CREW(スワローズクルー)のファンクラブ会員の声を受けて会員特典を見直し
技ありのレコメンド機能|TikTok
Bytedanceが運営する、ショートムービープラットフォーム「Tik Tok」。同社は2022年で創立から10年が経ちますが、いまやTik Tokのアクティブユーザー数は世界で10億人となっており、国内でも10〜20代の若者を中心に1700万人が利用するまでに成長しました。
Tik Tokがカスタマー・エクスペリエンスを向上させるために取り組んでいるのは、レコメンド機能における「フィルターバブル」という課題です。
フィルターバブルとは、ユーザーの興味・関心のあるコンテンツのみがおすすめとして表示され続けることで、それ以外の情報が手に入りにくくなるWeb上の問題を指します。
おすすめ機能は一見すると便利ですが、ユーザーの検索履歴やクリック履歴などのデータを基にした提案であるがゆえに、「偶然発見する」という機会は失われ、視野が狭くなることがデメリットです。
Tik Tokにも「レコメンド」機能があり、ユーザーの興味を引きそうな動画は随時おすすめしています。しかし、そのアルゴリズムが工夫されており、レコメンドの中にユーザーの興味と異なる動画が組み込まれるようになっています。
これにより、ユーザーはレコメンドから新たな分野に興味を持ったり、それまで知らなかったクリエイターと出会ったりできます。このレコメンド機能により、ユーザーがTik Tokに飽きてしまうことを防いでいるそうです。
同じような動画ばかりがレコメンドされた場合、そのジャンルに飽きてしまうとTik Tokの利用自体をやめてしまうユーザーも出てくる可能性があります。しかし、いつもとは違ったレコメンドによって新たな世界を発見すれば、Tik Tokに対して飽きにくくなります。
※参考:TikTokが「おすすめ」に動画をレコメンドする仕組み
アバターで行く伊勢丹新宿店|株式会社三越伊勢丹ホールディングス
大手百貨店を擁する株式会社三越伊勢丹ホールディングスは、業界の中でもデジタル事業に力を入れていることで知られる企業です。特に、2020年に始まった新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって客足が遠のいて以降、同社のデジタル戦略は注目を集めるようになりました。
三越伊勢丹では、「売り場」ではなく「お買い場」という言葉が使われています。これは、店頭のフロアを、商品を販売する企業側の視点ではなく、購入する顧客側の視点で捉えるための考え方の表れです。
同社はこうした姿勢に基づき、緊急事態宣言による休業が続く間も、顧客の求める買い物体験を社内で話し合うなど、カスタマー・エクスペリエンス向上のためのサービスを模索し続けていました。
そうした経験から生まれたのが、2020年11月リリースの「三越伊勢丹リモートショッピングアプリ」と、2021年3月スタートの仮想空間サービス「REV WORLDS(レヴワールズ)」です。
「三越伊勢丹リモートショッピングアプリ」では、ビデオ通話で店頭スタッフに商品を見せてもらったり、チャットで画像を見ながらテキストによる接客を受けたりして商品を購入できます。「REV WORLDS」は仮想伊勢丹新宿店にアバターを使って買い物に行けるコンテンツです。
これらのサービスのメリットは、自宅にいながら「予期せぬものとの出合い」を提供できることだといいます。
従来のECサイトは便利ではあるものの、販売員からの提案は受けられません。これらのサービスを活用すれば、自宅にいながらリアルに近い接客を受けられます。
※参考:「お買い場」の力を最大限に活かす。三越伊勢丹のデジタル組織の再編とアプリ開発 
オンラインで救う孤育て|FUNFAM株式会社
食器や調理器具の企画デザイン、料理イベントの運営、飲食店のプロデュースなどを行うFUNFAM株式会社。育児向けIT商品・サービスのコンテスト「BabyTech® Awards 2022」で授乳と食事部門の大賞を受賞した「ごかんごさい」も、同社が手掛けるサービスです。
FUNFAMは、コロナ禍によってオフラインの料理教室を開催できず、人との接触が減ったことがきっかけで、いわゆる「孤育て」問題に目を向けました。
孤育てとは、育児に関する相談ができなかったり、助けを得られなかったりすることが原因で、孤立したまま子育てをする状況のことです。育児ノイローゼやDVなどに発展する可能性もあり、社会的に大きな問題であるといえます。
株式会社ベビーカレンダーによる「孤育て」実態調査でも、コロナ禍になって孤独感が増したと回答した母親は回答者の7割を超えました。そこでFUNFAMは2020年6月、強みである「食」を通じたオンラインサービス「ごかんごさい」をスタートしています。
「ごかんごさい」は、生後5カ月〜18カ月の乳幼児向け離乳食を毎月届けるのがベースのコンテンツで、届いた食材にひと手間かけて完成させるレシピ構成になっている点が特徴です。このスタイルは、まるごとレトルトの離乳食を与えるときに生じる「子どもに手をかけてあげられない」という罪悪感を軽減するために考えられました。
また、育児の悩み相談も可能なオンライン離乳食教室や、専用のレシピサイトも用意し、利用者が他の保護者とつながることのできる仕組みも構築しました。
初めての育児のときなど、情報や商品、サービスは充実していても、結局何がいいのかわからないという悩みが常につきまといがちです。そこで、FUNFAMの「ごかんごさい」は離乳食の宅配と、オンライン離乳食教室・悩み相談をセットにし、子育てに悩む保護者の孤立を防ぐようにしています。
※参考:世界初オンライン料理教室体験付き【宅配離乳食BOX「ごかんごさい」】スマイルママプロジェクト始動!
メタバースでサーキットへ|株式会社ビフロスト
株式会社ビフロストは、グラフィックデザインの制作を中心に、動画編集やメタバース事業まで幅広く手掛けるデザイン事務所です。2013年に設立されて以来、車関連の雑誌やポスターなどのデザインも制作してきた実績があります。
コロナ禍において車関連のイベントの開催が制限されたり、サーキットへ足を運ぶ人が激減したりして、売上げを確保するのが難しい企業が多くありました。
そこでビフロストは、ドリフト走行技術を競い合うことで知られるモータースポーツ選手権「D1 GRAND PRIX」を仮想空間であるメタバースで開催できないかと考えました。
その後、SDK「Agora」を採用して構築したバーチャル空間「D1メタバースタ」では、ユーザーはアバターとして参加し、競技の生配信をリアルに現場にいるように見られます。
「D1メタバースタ」では、参加者同士でチャットや音声通話、リアクション機能やエモート機能があるため、参加者は競技だけではなくコミュニケーションも楽しめます。これにより、コロナ禍でも同じ趣味を持つ人同士がバーチャル空間のイベントで出会える機会ができ、ファンエンゲージメントも向上しているそうです。
自宅でビューティカウンセリング|palpat 株式会社
palplat 株式会社は、美容に関するプラットフォームの企画・開発・運営、最先端テクノロジーのコンサルティングなどを行う企業です。2021年10月には、SDKの「Agora」によって日本初のビューティーカウンセリング専門サイト「blush」をリリースしたことで知られます。
palplatはもともと、「“ひと”とデジタルの融合で体験のあり方を再創造する」をミッションとするため、デジタル分野におけるカスタマー・エクスペリエンスの向上に力を入れている点が特徴です。「blush」の開発段階でも、カウンセリング時に肌の状態を確認できる画質が整っているか、ビデオ通話がスムーズにできるかなど、細部までこだわりました。
「blush」のビューティーカウンセリングでは、スキンケアやメイクの方法、パーソナルカラー診断など、美容に関するあらゆることをオンラインで相談できます。ユーザーは自宅にいながら自分の悩みを気軽に相談できるのと同時に、カウンセラーにとっても普段の職場とは違った働き方が可能となっています。ユーザーとサービス提供者双方にメリットがある仕組みと言えるでしょう。
今後は化粧品メーカーとの提携も検討しており、カウンセリングを通じて商品の購入もできるサービスを目指しています。
 まとめ
まとめ
カスタマー・エクスペリエンスの向上に成功している企業は、「顧客は何を求めているか?」という問いを客観的なデータを基にしっかりと掘り下げて分析している傾向があります。
またデジタル分野では、特に商品やサービスを通して「偶然の発見ができるか」「デジタル上でもリアルに近い人とのつながりを感じられるか」といった点が重視されています。
もし、自社のカスタマー・エクスペリエンスに関する施策が思いつかずに悩んでいる場合は、改善の出発点である顧客の声について、きちんと拾えているかどうかを検証するのがおすすめです。この点が徹底できれば、具体的な施策のイメージも湧きやすくなるのではないでしょうか。