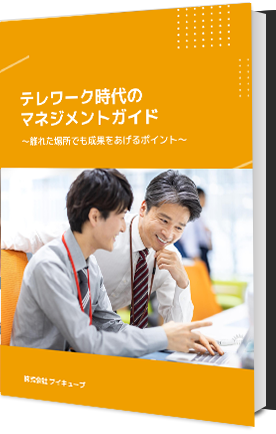メンバーシップ型雇用とは?メリットやデメリット、ジョブ型雇用との違いを解説

日本国内の企業では、従来その多くが従業員の採用前に業務内容や勤務地などを限定せずに雇用契約を結び、雇用された側は割り当てられた業務に従事するという雇用システムでした。これを「メンバーシップ型雇用」と言います。
一方で、近年さまざまな企業が「ジョブ型雇用」を導入しています。これは業務内容(ジョブ)・勤務地・労働時間などの条件を明確に決めて雇用契約を結ぶシステム。リモートワークやテレワークの導入が増えるなか、専門的な人材の確保などに適したジョブ型雇用に注目が集まっています。
両社の違いはどういった点にあるのでしょうか。ここではメンバーシップ型雇用について、そのメリット・デメリットをはじめ、ジョブ型雇用との違い、これからの雇用制度と課題などについて解説します。
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
メンバーシップ型雇用とは?
メンバーシップ型雇用とは、企業が人材を採用する際に、業務の内容や勤務地などを限定せず雇用契約を結び、雇用された側は割り当てられた業務に従事するという雇用システムです。
戦後の国内企業の間で広く採用されてきたシステムで、終身雇用を前提として、総合職として新卒一括採用を行う日本独特のシステムです。
企業は、能力やスキルよりも、人間性やポテンシャルを重視しながら新卒者を一括採用します。採用後は合同研修やOJTなどで教育を行い、定期的な配置転換によってキャリアアップを図るとともに、広範囲に渡る知識や経験を持つジェネラリストを育てていくという仕組みになっています。
このメンバーシップ型雇用は、長期雇用を前提としています。そのため企業は、将来を見据えてバランスの良い人材や幹部候補を長期的に育成できます。
言い換えれば、メンバーシップ型雇用は「仕事」ではなく「人」に賃金を支払う雇用制度であり、年齢や勤続年数に応じて報酬がアップする年功序列制度とイコールになっているケースが多くあります。そのため「仕事に人を合わせる」のではなく「人に仕事を合わせる」働き方と表現されることもあります。
業務で必要な能力やスキルはもちろん大切ですが、それ以上に組織への帰属が求められるのも特徴といえます。長期的かつ安定的な労働力を必要とした日本の高度経済成長期を支えたのが、このメンバーシップ型の雇用システムなのです。
ジョブ型雇用との違い
一方ジョブ型雇用とは、企業が人材を採用する際に、業務内容(ジョブ)・勤務地・労働時間などの条件を明確に決めて雇用契約を結び、雇用された側はその契約の範囲内でのみ働くという雇用システムです。
業務内容は、職務陳述書(ジョブディスクリプション)によって規定されています。ひと言で表現するならば、「仕事に人を合わせる」雇用システムです。
ジョブ型雇用は、業務内容が明確に決まっていることから仕事の専門性が高く、業務範囲は限定的であることが特徴です。
また、成果によって評価されるため、ジョブ型雇用を実現するにはその分野におけるスペシャリストであることが望まれます。
ジョブ型雇用は、欧米を中心に世界的に導入されている主流の働き方です。
メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の違い
|
メンバーシップ型雇用 |
ジョブ型雇用 |
|
|
仕事の範囲 |
|
|
|
求められる・育つ人材 |
|
|
|
報酬制度 |
|
|
|
主な採用方法 |
|
|
|
転勤 |
|
|
|
教育制度 |
|
|
メンバーシップ型雇用のメリット
批判的に語られがちなメンバーシップ型雇用ですが、一括採用した新卒者を長期的かつ計画的に育成することで、企業を持続的に成長させていく仕組みは、戦後の日本が高度経済成長を遂げるうえで大きな推進力となったといえます。企業と従業員にとってメリットも多くある雇用システムなのです。
企業のメリット
配置転換ができる
企業は従業員を長年雇用する代わりに、会社の経営方針や育成などの観点から従業員を他の部署や勤務地に迅速に異動させることができます。
チームワークが強化される
長期にわたって同じ企業や組織で働き続けることで、企業の一員としての自覚を持ちやすくなります。そうした帰属意識が高まることで仕事へのモチベーションが上がり、その結果、チームワークが高まり、従業員同士が助け合いながら業務を進められます。
長期的かつ計画的に人材を育成できる
時間をかけて、長期的かつ計画的に幹部候補を育てることができます。企業は終身雇用を前提に一括採用しているので、部署を定期的に変えたり、さまざまな業務を経験させたりすることで、さまざまな方面に精通したバランスの良いジェネラリストな人材を育成できます。
新卒一括採用により採用コストを抑えられる
新卒・中途を問わず不定期に採用する「通年採用」は、定期的に求人広告を出したり説明会を開くなどしてコストがかさみます。一方で、春に新卒者を一括採用する新卒一括採用は、短期間でまとめて採用できるので、通年採用よりコストを抑えられます。
また、卒業後の就職先を探している学生をターゲットにすることで、コストを抑えつつも若くて優秀な人材をより確保しやすいともいえます。
従業員のメリット
解雇されにくい
メンバーシップ型雇用は終身雇用と年功序列を前提としているので、従業員は一度採用されれば解雇されにくいといえます。企業ごとに労働組合を保有していることが多く、従業員は急な解雇などを気にせず安心感のある環境で働けます。
研修など人材育成の場が用意されている
企業が継続的に成長していくためには、長期的な視野で人材や幹部候補を育成していくことが欠かせません。そのため従業員には、キャリアアップのための研修などといった人材育成の場が数多く用意されています。
メンバーシップ型雇用のデメリット
当然ですが、メンバーシップ型雇用にはデメリットもあります。
企業のデメリット
スペシャリストが育ちにくい
メンバーシップ型雇用の企業は、定期的な配置転換によってジェネラリストを育てていける反面、専門的なスキルを持つスペシャリストが育ちにくい環境であるといえます。
専門的な仕事が継続してあるときは、部分的にジョブ型雇用を行うなどしてスペシャリストを見つける必要があります。
テレワークに向いていない
メンバーシップ型雇用の場合、業務の範囲が明確に決まっていないことが多く、上司とのコミュニケーションによって業務内容が割り振られるケースがよくあります。
テレワークの場合、業務内容が見えづらく、密なコミュニケーションが取りにくい側面もあるため、メンバーシップ型雇用を採用している企業ではうまく機能しないこともあるかもしれません。
人件費がかさむ
従業員の給与は年功序列で昇給し、年齢や勤続年数を重ねるほど高くなるので、実際の働きぶりと関係なく、企業は規定の給料を支払うことになります。
また、高齢になるにつれて生産性が下がる従業員がいたり、企業が経営不振に陥っていても簡単に従業員を解雇できなかったりするため、人件費は大きな負担となります。
従業員のデメリット
会社の都合で条件を変更される
業務内容や労働時間、勤務場所が契約で限定されていないため、企業の都合で部署の異動や転勤、残業を命じられることがあります。従業員は自分で業務を選ぶことができないので専門性を磨きにくく、人によっては配置転換などによって幅広い職種を経験することになります。
年功序列などの給与形態への不満
従業員がどれほど優秀で大きな成果を上げたとしても、年齢が若ければ賃金は上がりづらく、より良いポジションに就きにくいのが現状です。年功序列などによる給与形態によって若手のモチベーションが下がったり、不満がたまりやすかったりするという点は課題といえます。
これからの雇用制度と課題
2020年、日本経済団体連合会(経団連)の中西宏明会長は、「一つの会社でキャリアを積んでいく日本型の雇用を見直すべき」と提言し、話題になりました。つまり、メンバーシップ型の雇用システム自体が時代に合わなくなってきたのです。
近年ではテレワークの普及や働き方の変化に伴い、メーカーや流通など日本を代表する大手企業でもジョブ型雇用の導入が進んでいます。こうした動きが広まると、一人ひとりの仕事の専門性が高まり、業務範囲はより限定的になっていくと考えられます。
ただ、業種や業態によってジョブ型雇用が適さない場合もあります。長年の経験や技術を要するものづくりの現場や、多様な業務を一人でこなす必要のある企業などでは、メンバーシップ型雇用のほうが有用な人材を育成できることもあります。
ジョブ型雇用を導入すべきかどうかは、会社の規模や状況によって異なります。雇用制度と連動する採用・評価・報酬制度も変更する必要があるため、すぐに移行することは難しいでしょう。
まずはジョブ型雇用のメリット・デメリットを理解し、実情に即したかたちで少しずつ改革していくことを検討する必要があります。
また、日本の社会全体でジョブ型雇用が広く浸透するには、大学制度なども含めた改革が必要になります。新卒者が専門的なスキルや能力を身につけるためには、学校はそのための教育、すなわち職業教育を用意しなければなりません。
メンバーシップ型雇用システムが前提であれば、具体的な資格や知識より、与えられた仕事に一生懸命に取り組み、チームメンバーと目標を達成していくコミュニケーション能力が大切になります。
実際にジョブ型雇用を導入するにあたっては、まず会社の上層部や管理職を対象にするのがいいかもしれません。こうした層は専門的なスキルを求められることが多くなるためジョブ型雇用が適しており、労働組合に加入している一般社員に比べてジョブ型雇用を導入しやすいといえます。
参考:日本も新卒採用よりジョブ型雇用へ 就社意識改めよう|NIKKEI STYLE
まとめ | 最適な雇用システムを見つける
上述したように、戦後の日本の経済成長を支えたメンバーシップ型雇用は、いまの時代の実情に則さないケースが増えてきました。時代の変化に対応していくためにも、人事制度改革は避けては通れないことの一つです。
業種や業態によってはジョブ型が適さない場合があるので、従来のメンバーシップ型雇用のメリットを生かしつつ、デメリットの部分はジョブ型雇用に少しずつ移行しながら、企業にとって最適な雇用システムを導入していきましょう。