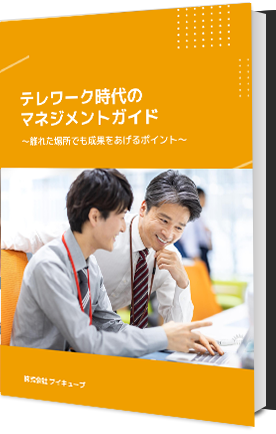ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用のメリット・デメリット、報酬の違いを解説

テレワークが普及して働き方が変化している中、「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」に注目が集まっています。
企業にとっては、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用を使い分けて採用することで、効果的に人員配置を行うことができます。また、テレワーク環境下でも、設定した目標を達成して成果を上げやすくなります。
本記事では、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の意味、メリット・デメリット、報酬の違いなどをわかりやすく解説します。
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用のそれぞれの意味を簡単に確認しましょう。
ジョブ型雇用とは
ジョブ型雇用とは、「仕事に対して人が割り当てられる」仕組みの雇用形態です。職務内容や勤務地、勤務時間などの条件が、職務記述書によって規定されています。
職務内容が明確に決められているため、ジョブ型では業務範囲が限定的で、専門性が重視されます。
メンバーシップ型雇用とは
メンバーシップ型雇用とは、「人を採用してから仕事を割り振る」仕組みの雇用形態です。職務内容や勤務地、勤務時間などを限定せずに、総合職として会社に合っている人を採用します。
ジョブ型とは対照的に、幅広いスキルや視野を持ったジェネラリストが育成されていきます。勤務時間などに明確な規定がないため、異動や転勤、残業が命じられることがあります。
ジョブ型雇用のメリット・デメリット
「仕事に対して人を割り当てる」ジョブ型雇用のメリット・デメリットを解説します。
企業側のメリット
企業側は、従業員の職務内容・役割が明確になっていることから、専門性の高い人材を採用しやすくなります。職務内容が明確だからこそ正当に評価しやすいため、高い生産性を維持しながらテレワークを推進できます。
また、スキルに合った給与を設定できるのもメリットです。メンバーシップ型なら年功序列であることが多く、勤続年数が長いという理由だけで高い給与を払う企業が多いですが、ジョブ型であれば事前にスキルに見合った給与設定が可能です。
企業側のデメリット
反対に、ジョブ型の場合は会社都合の転勤や異動をさせることができないので、人員調整や補充をしづらいのがデメリットになりえます。その上、スキルで採用するため、ジェネラリストを育てにくいです。経営方針が変更になり、ジョブ型のスキルが不要になった場合などに、ジョブ型雇用の従業員に他の業務を任せることはできません。
また、ジョブ型は採用の難易度が上がります。高い専門性を持つ人材は引く手あまたで、より魅力的な会社に転職します。すぐに採用できるわけではないことと、採用できたとしてもより待遇のよい企業に引き抜かれてしまうリスクがあります。
求職者のメリット
求職者側にとって、ジョブ型は職務記述書によって職務内容が定められているため、自分の専門領域の仕事のみに集中できます。ジェネラリストとして専門外の仕事をする必要がありません。
また、専門性の高い職業のため、スキルに見合った給与をもらうことができます。専門スキルを磨くことができれば、職務レベルとともに給与が上がる可能性もあります。
求職者のデメリット
反対に、ジョブ型雇用は、スキルが不十分だと見なされると契約終了となることもあります。そのため、専門性を高めるべく日々の自己研鑽が必要です。
また、スキルが必要とされる業務がなくなったら解雇される可能性があります。
メンバーシップ型のメリット・デメリット
「採用した人に対して仕事を割り振る」メンバーシップ型雇用のメリット・デメリットを解説します。
企業側のメリット
企業側にとって、ジェネラリストを育成できるメンバーシップ型では、欠員がでたときに迅速に従業員を他の部署に異動させることができることがメリットです。適切な人員配置ができることは、効率的な経営につながります。
また、都度必要なスキルを持った人材を採用するジョブ型とは異なり、新卒一括採用でメンバーシップ型雇用は可能です。その結果、採用コストを削減できます。
企業側のデメリット
反対に、幅広い業務を担う総合職として採用するため、従業員に専門的な知識や技能を身に着けて熟練させることは困難です。専門性の高いスキルを必要とするのであれば、ジョブ型雇用が適しています。
一度採用すると解雇しづらいため、能力がなく会社への貢献見込みも少ない従業員であっても雇用し続ける必要があります。年功序列の給与体系であれば、勤続年数に応じて給与を上げる必要も出てくるため、企業にとってデメリットになります。
また、テレワークを実施している会社では、職務内容が明確に決まっていないメンバーシップ型だと人事評価がしにくいというデメリットもあります。対面で密にコミュニケーションを取りづらい状況で、業務内容を割り振り適切に評価することは難しいです。
求職者のメリット
メンバーシップ型雇用では、スキルベースではなく会社に合う人が採用されているため、結果として企業や組織内でのチームワークが強くなります。研修やトレーニングが用意されていて、組織の結束力が強まる傾向にあります。
また、終身雇用を前提とした雇用のため、長期的に働けることが約束されています。不当な解雇を受けることがないことは、求職者のメリットです。
求職者のデメリット
反対に、ジェネラリストとしての採用の場合は、賃金や待遇で男女格差が生まれやすいともいわれています。出産などによりキャリアが一時的に中断した女性は特に、男性と比べて給与や任される仕事内容に差が生まれやすいです。年功序列のため、勤続年数による給与の差も生じます。
また、正規雇用と非正規雇用とでの待遇差が大きいのも、メンバーシップ型雇用のデメリットです。同様な成果を出したとしても、正規雇用のほうが優遇されやすいです。
報酬の違い
ジョブ型とメンバーシップ型の報酬の違いを見てみましょう。
ジョブ型
ジョブ型雇用では、「職務給」を採用しています。年齢や勤続年数に関わらず、高いスキルや能力があると、給与アップを見込めます。
メンバーシップ型
メンバーシップ型雇用では、「職能給」を採用しています。給与は勤続年数に影響される傾向があります。
欧州、日本との違い
欧州と日本では、どちらの雇用形態が主流なのでしょうか。
欧州では、ジョブ型雇用が主流になっています。一方、日本では、メンバーシップ型雇用を雇用形態として採用しています。日本型雇用ともいいます。
ただし、日本でもメンバーシップ型雇用の維持が難しくなってきています。技術革新が進む中で、専門スキルを備えた人材が必要になってきているからです。また、伸び悩む経済状況の中で、年功序列型の賃金制度が採用されているメンバーシップ型雇用を続けるのは、企業のコストの観点からも難しくなってくるでしょう。
テレワークが推進される中、今後は日本でもジョブ型雇用を広げるための取り組みが進むと想定されています。
新卒採用方法の変化
以前は新卒一括採用では総合職として、能力ではなく、企業とのマッチングやポテンシャルを見ての採用が一般的でした。現在では、学生の能力・適性を見て企業側からオファーを送るOfferBoxや、KDDIでは、初期配属領域を確約しない「OPENコース」と初期配属領域を確約する「WILLコース」に分けての採用、日立製作所では内々定とともに配属先が決定する「ジョブマッチング」の制度を取り入れるなど、新卒採用にも変化が見られます。
一方欧州でも専門スキル以外の能力の必要性は理解しており、ゼネラリストを育てられる仕組みは注目されているため、一概にメンバーシップ採用が古いとは言えません。日本やそれぞれの企業に合った採用方法を模索する必要があります。
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の比較表
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用を比較し、まとめた表は以下の通りです。
|
ジョブ型雇用 |
メンバーシップ型雇用 |
||
|
特徴 |
|
|
|
企 業 側 |
メリット |
|
|
|
デメリット |
|
|
|
求職者 |
メリット |
|
|
|
デメリット |
|
|
|
|
報酬 |
「職務給」: スキル |
「職能給」: 勤続年数 |
|
|
国 |
欧州に多い |
日本に多い |
|
まとめ|ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いを理解し、会社に合う雇用形態を取り入れよう
今回はジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用のメリット・デメリット、報酬の違いなどを解説しました。
テレワークが広まる中、適切な人事評価を行い、生産性高く業務を遂行することができると考えられているのは、ジョブ型雇用です。会社の業務内容によって、必要なスキルや専門性は異なります。
もしメンバーシップ型雇用だけでなく、ジョブ型雇用も取り入れるなら、採用・雇用・評価・報酬制度も変更する必要があります。すぐに移行せずに、どの職種において適しているのかよく検討してみてはいかがでしょうか。