職場環境の改善は必須!働きやすい職場を作るためのアイデアとは
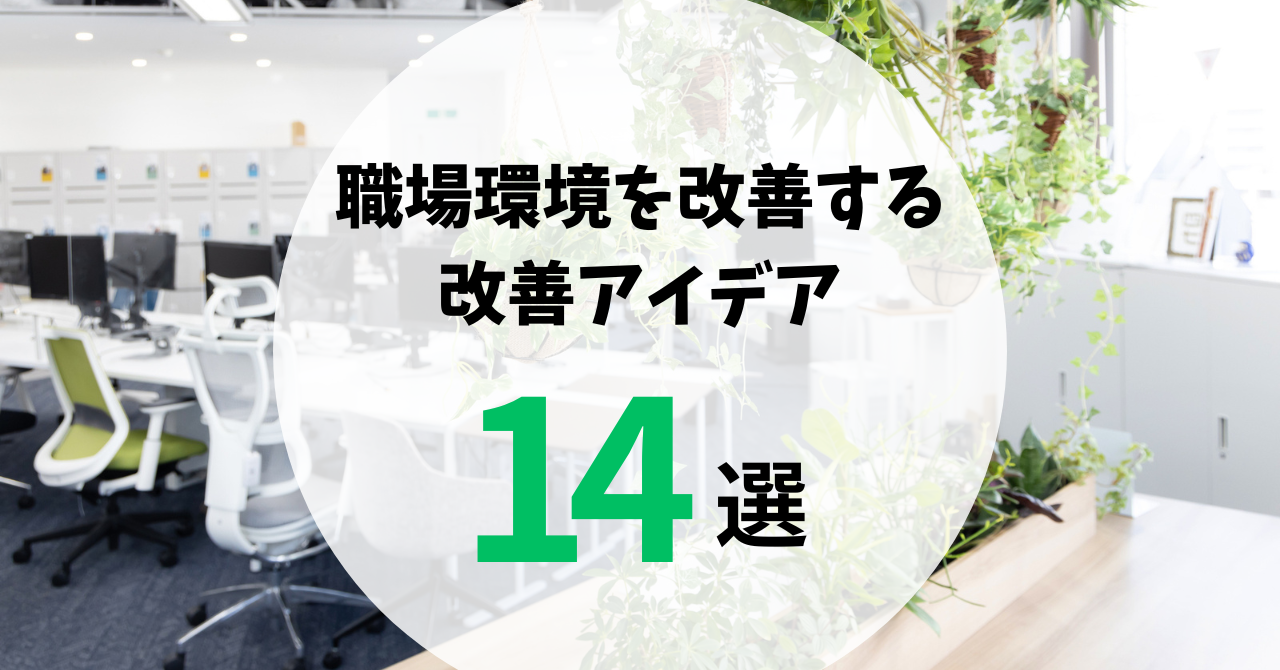
現代人の働き方は、革新的なデジタル技術の進化の中で多様化しつつあります。こうした変化にさらされる環境下で企業が成功を収めるには、高い意欲を持って業務にあたる社員の存在が不可欠です。
しかし、ただ業務ができる場所を与えるだけでは、社員満足度やモチベーションを高めることはできません。これからの企業は、職場環境の改善にしっかりと取り組み、社員一人ひとりの幸福感をアップさせ、生産性の向上につなげる必要があります。
今回は、「オフィス環境」「働き方」「コミュニケーション」「知識共有とスキルアップ」の4つの観点から、職場環境の改善につながるアイデアを紹介します。現代の職場が抱える課題の解説とともに、社員がより働きやすくなるための施策を提案するので、ぜひ参考にしてください。
【無料お役立ち資料】オフィス環境改善ガイド
従業員の生産性を向上させるオフィスづくりのポイントを、最新トレンドと合わせて解説する資料を配布しています。
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
オフィス環境を改善するためのアイデア
働く上での物理的側面であるオフィス環境の改善には、以下のようなアイデアがあります。
- コミュニケーションスタイルに合わせたスペース
- 快適な作業スペース
- 光と緑
- リラクゼーションエリア
順にアイデアをご紹介します。
コミュニケーションスタイルに合わせたスペース
オフィスフロア以外に、Web会議用の個室ブースや対面用の会議室を整える施策は、オフィス環境の改善につながります。プライバシーや集中が保てるか、音響環境は適切かといった点は、社員の生産性やコミュニケーションの質を左右するからです。
弊社、株式会社ブイキューブが実施した「ニューノーマルな働き方におけるWeb会議の実態調査」では、やむを得ず自席でWeb会議を行っている現状が判明しました。
理由として顕著なのは「会議室が足りないから」「会議室を一人で占有するのは気が引けるから」というものです。しかし、自席でWeb会議に参加する社員の声を「うるさい」と感じたことのある人の数は、約半数に上ることも判明しています。
株式会社帝国データバンクの調査によると、アフターコロナになり社内会議は対面が61.8%で最多となった一方、社外との会議は対面とオンラインの混在が50.2%と半数を超えるそうです。今後もWeb会議、対面会議それぞれに適したスペースの確保は職場環境の改善に役立つといえるでしょう。
出典:アフターコロナ、社内会議は61.8%が「対面」に 社外との会議は「対面・オンライン」混在が5割超える | 株式会社帝国データバンクのプレスリリース
Web会議用の個室ブースであれば、大規模な工事をせずともオフィス家具のように設置が可能です。社員のコミュニケーションスタイルに合ったスペース確保の際は、検討をおすすめします。
例えばブイキューブの提供する「テレキューブ」は完全個室のボックス型の個室ブースで、高い防音性と快適な居住性が特徴です。サブスクリプションプランでも提供しているため、購入するよりも手軽に導入できます。複数用の製品であれば、工事なしで会議室不足の解消にも繋がります。
オフィス用の個室ブースはどう選ぶ?タイプ別の特徴や抑えておきたい消防法への対応などのポイントを紹介
オフィス用の個室ブースについては「オフィス用の個室ブースはどう選ぶ?タイプ別の特徴や抑えておきたい消防法への対応などのポイントを紹介」の記事で詳しく解説しています。
快適な作業スペース
コクヨ株式会社が2019年に実施した「デスクワークの実態と健康意識に関する調査」によると、オフィス家具は社員の働きがいや自社への愛着へ影響を及ぼすことがわかりました。
この調査では、デスクワーク環境への満足度が高い社員ほど、「働きがいがある」「(仕事が)好きである」と回答する傾向が見られます。
一方で、デスクワークのためのオフィス家具がよい姿勢を保つのに配慮されていないと回答した人が59%、デスクワーク環境に不満があると回答した人は53%と過半数を超えました。
つまり、快適な作業スペースは仕事へのモチベーションや生産性を向上させる効果が見込めるにもかかわらず、その施策は不十分であるということです。
このことから、オフィス環境の改善には人間工学に基づいたデスクやチェアを導入し、長時間の作業による体への負担を減らす工夫が有効でしょう。例えば、広さが十分で、デスクやチェアの高さが調節できるといった点は、快適さにつながります。
出典:日本のオフィスワーカー1,000 名に「デスクワークの実態と健康意識」に関する調査を実施
オフィスワーカーの約 6 割が、オフィス家具の姿勢への配慮に不満 デスクワーク環境の満足度が、働きがいや自社への愛着に影響
「令和4年 国民生活基礎調査」によれば、日本人が自覚する不調の第1位は腰痛、第2位は肩こりです。自然な形で健康への配慮ができる環境を目指してみてください。
光と緑
近年、オフィスにバイオフィリアを導入する動きが注目されています。バイオフィリアとは、自然を意味する「バイオ」と愛情を意味する「フィリア」を組み合わせた言葉です。
米国の行動生物学分野の権威、Edward Wilson(エドワード・ウィルソン)博士が提唱した概念で「人は自然とのつながりを本能的に求める」という考えを指します。
オフィス環境におけるバイオフィリアには「植物や花を置く」「自然光を取り入れる」「空気循環を改善する」「木材のオフィス家具を設置する」「森や川の音や香りを取り入れる」といった方法があります。その具体的な効果は、ストレスの軽減、生産性や創造性の向上です。
一般社団法人花の国日本協議会が実施したアンケート調査では、コロナ禍で自宅に植物や花を飾りたくなった人は90%、その理由の第1位は「癒やされたい」、第2位は「元気をもらいたい」でした。
また、室内緑化に取り組む株式会社グリーバルが川崎市庁舎で働く職員を対象に行った実験によると、植物がオフィス環境の改善に効果を上げたこともわかっています。
例えば、執務室に植物があることで、作業効率アップを実感した人は8%増、オフィスへの満足度は22%増、創造性アップを感じた人は14%増といった結果が見られました。このように、自然を感じられる空間はオフィス環境の改善に効果的です。
出典:SERVICE バイオフィリックデザイン | greeval
リラクゼーションエリア
厚生労働省の「令和4年 労働安全衛生調査」によると、仕事や職業生活に強い不安や悩み、ストレスを感じる人の割合は82.2%と非常に高いことがわかっています。その理由として目立つのは「仕事の量」「仕事の失敗、責任の発生等」です。
高ストレス状態が続く環境下では、健康が損なわれたり、ミスが発生したりする可能性が高まります。休憩や同僚との雑談ができるリラクゼーションエリアは、ストレスの軽減や集中力の回復、創造性の促進などの点で重要といえるでしょう。
実際、オフィス家具を取り扱うプラス株式会社の「働き方に関するWEB調査2023年」では、オフィスに対する不満の第1位が「カフェやラウンジなどのスペースがない、足りない」で35%でした。
同調査では、雑談の効果として「気分転換やリフレッシュ」「良好な人間関係や雰囲気作り」を挙げた人が約4割にも上ります。さらに、こうしたカジュアルなコミュニケーションができる環境にある社員ほど、職場への満足度が高いことも明らかになりました。
出典:『働き方に関するWEB調査2023年』 “コミュニケーション不足” アフターコロナのオフィスに求められる要素とは? | オフィス移転・オフィスリニューアルのプラス株式会社ファニチャーカンパニー
強いストレスを感じる人の多い日本では、こうしたリラクゼーションエリアの設置がオフィス環境改善の鍵を握るといえます。
働き方を改善させるためのアイデア
社員のワーク・ライフ・バランスに影響を与える働き方の改善では、以下のアイデアを提案します。
- フレキシブルな時間制度
- リモートワークの推進
- 健康管理支援
フレキシブルな時間制度
総務省の「令和4年版 情報通信白書」では、日本の生産年齢人口(15~64歳)は2050年に5275万人となり、2021年と比較して29.2%減少すると見込まれています。
また、社員の生活リズムや、育児・介護などの事情は多岐にわたっており、もはや一律の勤務時間が全ての人に適しているとはいえません。フレキシブルな時間制度の導入は、こうした状況下で幅広い人材を確保したり、社員の働きやすさを改善したりすることにつながります。
例えば、始業と終業の時刻を社員が決められるフレックスタイム制はその代表でしょう。コアタイムを設けている場合は、時間帯の短縮も改善策のひとつです。
フレックスタイム制の採用が難しければ、勤務時間を選択制とする方法があります。同じ8時間勤務でも「9時~18時」「10時~19時」「11時~20時」から選べるようにすれば、生活リズムに合わせた働き方の支援が可能です。
さらに、1つのフルタイム職務を2人以上で分担するジョブシェアリングでは、午前中はAさん、午後はBさんであったり、月・火はAさん、水~金はBさんといった働き方を実現できます。家庭事情のある社員の離職防止や、多様な人材確保につながるのがメリットです。
リモートワークの推進
株式会社ネクストレベルが行ったアフターコロナの働き方に関する調査によると、コロナ禍で9.5%まで減少した完全出社体制は、コロナ後に38.5%まで回復しているそうです。
一方で、完全出社・ハイブリット勤務(出社とリモートワークの混在)・リモートワークという3つの働き方を比較すると、完全出社の満足度が最も低く、リモートワークの満足度が最も高いこともわかりました。
同調査では、リモートワークへの満足度は男女共に約8割という高さです。リモートワークが高い支持を得る理由には、通勤の負担が減ることや、飲み会がなくなり時間とお金に余裕が生まれることなどが挙げられています。
出典:アフターコロナの働き方調査!フル出社が4倍に増加し、満足度は低下傾向に! | 株式会社ネクストレベルのプレスリリース
このことから、アフターコロナであってもリモートワークができる環境を維持・推進することは、社員の働き方改善に必要な施策といえるでしょう。例えば、リモートワークに必要な機材や、困ったときのサポート体制を整えることが重要です。
こうした取り組みは、地理的な制約のない採用活動を可能とするため、企業にとっても人材確保という点で強みとなり得ます。
健康管理支援
社員の健康管理支援は、生産性や満足度を向上させたり、健康問題による長期の病欠や離職を防いだりする役割があります。
コクヨ株式会社が実施した「デスクワークの実態と健康意識に関する調査」では、働く人の約9割が勤務中に健康や体調管理を意識できていないことが判明しました。
同時に、勤務時間を健康管理に活用したいと回答した人は「積極的に活用したい:31%」「活用したい:55%」と、8割を超えています。企業がこうした声に応えることは、働き方を改善するのに重要といえるでしょう。
出典:日本のオフィスワーカー1,000 名に「デスクワークの実態と健康意識」に関する調査を実施
オフィスワーカーの約 9 割が、勤務中に健康を意識していない 健康や体調管理のために勤務時間を活用したいという理想と現状が乖離
例えば、健康診断の検査項目を充実させる支援方法があります。健康診断には、実施が義務づけられている項目以外に付加健診やオプション検査が追加可能です。この費用を企業が負担することで、社員の健康問題の早期発見や治療につながります。
また、オフィスにフィットネススペースを確保して器具を設置したり、ジム会員費用をサポートしたりしてもよいでしょう。適度な運動はストレス軽減や、パフォーマンス向上に役立つからです。
さらに、メンタルヘルスケアプログラムの提供も検討してみましょう。
総務省の「令和4年度 総合的なメンタルヘルス対策に関する研究会報告書」によると、精神及び行動の障害による長期病欠者の数は令和3年の時点で15年前の約2倍となり、年々増加傾向です。メンタルヘルスへの予防的な介入とサポートは、長い社会人生活にとって必要不可欠といえます。
コミュニケーションを改善するためのアイデア
続いて、コミュニケーションを改善するためのアイデアを4つ紹介します。
- 1on1
- チームビルディング
- オープンスペースの活用
- 社内報の刊行
1on1
上司と部下が1対1で定期的に面談を行う、「1on1」。株式会社リクルートマネジメントソリューションズが2022年に行った「1 on 1ミーティング導入の実態調査」によると、社員数100人以上の企業のうち約7割が導入しているそうです。
導入の主な目的としては「社員の主体性・自律性の向上」「自律的キャリア形成の支援」「評価の納得性の向上」などが挙げられています。
1on1は、個々の社員と管理職にある人が直接的なコミュニケーションを取るため、継続的なフィードバックを促進できるのが特徴です。これにより、社員の成長支援やモチベーションの向上、課題の早期発見につなげやすくなるでしょう。
事実、同調査では1on1の導入が「上司と部下の関係性の改善」「社員のモチベーションアップ」「職場の雰囲気改善」といった効果を発揮していることがわかりました。
また、既に導入している企業であっても、その約6割が1on1を過去3年以内に取り入れたことも判明しています。企業にとっては比較的新しい施策ではありますが、社員それぞれの状態把握や、上司と部下のコミュニケーション不足に悩む場合は、1on1が状況を打開する可能性があるでしょう。
チームビルディング
チームビルディングは、組織内のコミュニケーション活性化やチームワークの強化、モチベーションアップにつながるといわれます。
株式会社ラーニングエージェンシーが2021年に実施した「組織・チームのあり方の変化に関する意識調査」によると、10年前と比較して社員に求められるスキルに変化が見られることがわかりました。
具体的には「個人として成果を上げる」ことへの期待値が12.5ポイント減少しているのに対し、「チームで協力して成果を上げる」ことへの期待値は44.1ポイントと大幅に上昇した形です。このことから、定期的に開催できるチームビルディング活動は重要度が高いといえます。
出典:【組織・チームの在り方を5,000人に調査】10年間で一般社員に期待されることが大きく変わった | ALL DIFFERENT株式会社のプレスリリース
チームビルディング活動には、専門のファシリテーターを招いて行うワークショップや研修、社内スポーツイベント、ボランティア活動などがあります。業務と切り離さずにチームビルディングを促進するなら、戦略会議とレクリエーションを組み合わせた合宿を行ってもよいでしょう。
また、日常の会議前にアイスブレイクゲームやロールプレイングゲームを取り入れるやり方であれば、導入への負担をかけずにコミュニケーションを活性化できます。部署単位の状況に合わせて、適切な施策を検討してみてください。
オープンスペースの活用
オープンスペースは、自席や会議室とは別に設けられた、自由利用を目的とする場所です。企業によっては、先ほど紹介したリラクゼーションエリアと役割を兼ねているケースもあります。
オープンスペースではノートパソコンを持ち込んで業務をすることもできるため、自席にいると関わりの薄い社員とのコミュニケーションが生まれるのがポイントです。
こうしたオープンな議論は部門間の壁を取り除き、お互いの知識共有や新しいアイデアの創出につながる可能性があります。組織内の分断によって有機的な活動が制限されている場合は、導入を検討するとよいでしょう。
ただし、オープンスペースを設ける際は、利用上のルールを明確にしておくことが大切です。例えば、Web会議や電話、飲食などをOKとするかどうかなど、社員の意見を取り入れながら決めることをおすすめします。特に、Web会議や電話では機密情報が取り扱われることもあるので、リスク管理をよく考えておきたいところです。
また、業務によっては自席や個室ブースでの集中が必要な場合もあります。オフィス設計はそうしたバランスも考慮しながら行うようにしましょう。
社内報の刊行
社内報は、企業文化の浸透・醸成や社員エンゲージメントの促進に寄与します。組織内のさまざまな情報を一元的に共有するコミュニケーション方法といえるでしょう。
株式会社Voicyが実施した「社内コミュニケーションに関する調査」によると、社内報を重要だと思う人の割合は72.6%と高いことがわかりました。
同調査では「親しみやすい内容であること」「時間や場所を選ばず確認できること」などが、社内報に求められる項目として挙げられています。これらのことから、社内報では業務以外の項目にも触れたり、Web媒体で発行したりする工夫が必要といえるでしょう。
例えば、従業員インタビューや社内イベントの報告、社員のお弁当紹介、ブックレビューなどの情報は、社員の興味を引きやすく、コミュニケーションのきっかけにもなります。また、Webや紙媒体以外に、社内ニュース動画を内部配信するのも方法のひとつです。
自社で一から社内報を作成するリソースが不足する場合は、社内報作成ツールを導入してもよいでしょう。Web媒体であれば、「いいね!」やコメントが可能なタイプも複数提供されています。
知識共有とスキルアップのためのアイデア
社員同士の知識共有や、キャリアにおけるスキルアップが課題の場合は、以下のような施策があります。
- 研修プログラムの充実
- メンターシップ制度
- ナレッジシェアリング
研修プログラムの充実
市場変化や技術革新が激しい現代は、企業の競争力を維持するための継続的な学習とスキルアップが欠かせません。研修プログラムの充実は社員のキャリア成長を促したり、企業のイノベーション力を強化したりする効果が期待できます。
株式会社グロースXの行った人材育成に関する課題調査では、企業内で実施した研修による社員のスキルアップを実感した管理職は7割を越えました。研修プログラムの方法では、オンラインコースの活用や社員主導のワークショップ、OJT、社外セミナーへの参加を採用する企業が目立ちます。
出典:【大企業の部長に聞く、人材育成の課題】約7割が研修による「従業員のスキル向上」を実感も、同じく約7割が「学びを実務で活かせていない」と課題 | 株式会社グロース Xのプレスリリース
一方で、研修プログラムを充実させたくても、適切な指導者や実施のための費用不足を課題とする企業もあるでしょう。施策導入の際は、限られたリソースを最大限に活用できるよう、自社の研修目的を明確にすることが大切です。
例えば、最新の業界知識を身につけさせたいのか、チームの生産性をアップさせたいのか、リーダーシップのスキルが必要なのかなど、目的に合わせた研修を取り入れてください。
メンターシップ制度
経験豊富な先輩社員が、対話を通じて後輩社員の成長をサポートするメンターシップ制度も、知識共有やスキルアップに有効でしょう。先輩への相談を通じて、新入社員・若手社員が課題発見や自律的解決をしやすくなるからです。
厚生労働省による「メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル」によると、メンター制度はメンター(先輩社員)・メンティ(後輩社員)の双方にプラスの影響があるとされます。
例えば、メンターの人材育成意識が向上する、メンティのモチベーションや知識・スキルがアップする、メンティの職場環境への適応度が上がる、といったものです。
メンターシップ制度は、メンターとメンティのマッチングが鍵となります。希望制や人事部による選定、適性検査を活用する方法など、やり方はさまざまですが、メンターが与えられるものとメンティが求めるものが合致するよう工夫しましょう。
なお、メンターシップ制度は1on1のような、上司と部下の組み合わせとは限りません。対話の内容も、キャリアや職場における課題・悩みを主に扱う点で、評価にウエイトを置く1on1とは異なります。
ナレッジシェアリング
株式会社プロジェクト・モードによるナレッジマネジメントに関するアンケートによれば、社員数が50人を超えると知識共有に課題が出てくるそうです。具体的には、ナレッジが属人化したり、必要な情報が効率的に探せなかったりする事象が発生します。
出典:【ナレッジマネジメントの実態調査】ナレッジ管理SaaS「NotePM」を提供するプロジェクト・モードが調査レポートを公開 | 株式会社プロジェクト・モードのプレスリリース
このことから、ナレッジシェアリングは効率的な問題解決や企業全体のパフォーマンス向上に重要といえるでしょう。
ナレッジシェアリングの方法には、ノウハウ共有会やプロジェクトのレビュー会、テックトーク(エンジニアの技術共有会)などの開催があります。ランチ&ラーンと称して、昼食を取りながらカジュアルな雰囲気の中で実施するのもやり方のひとつです。
また、社内データーベースに知識・技術を蓄積する場合は、検索機能を意識するとよいでしょう。必要な情報がすぐに検索できないと、いくら蓄積しても利用されないからです。ナレッジシェアリングには専用のツールもあるので、必要に応じて検討することをおすすめします。
まとめ
職場環境の改善は社員の満足度アップに直結するため、結果として企業の持続的な成長を促します。確かに、改善のポイントはオフィス環境や働き方、コミュニケーション、スキルアップと、多岐にわたるため、その取り組みには時間も労力も必要です。
しかし、改善への継続的な取り組みは魅力的な職場を作り出し、社員の物理的・精神的なウェルビーイングを促進させるでしょう。
企業が職場環境の改善を行う際は、社員アンケートなどで意見を募る姿勢も大切です。相互にコミュニケーションを取りながら、課題への優先順位をつけることで、自社にとっての有効的な施策が実現します。今回紹介したアイデアを参考に、ぜひ前向きに職場環境の改善を目指してください。
【無料お役立ち資料】オフィス環境改善ガイド
従業員の生産性を向上させるオフィスづくりのポイントを、最新トレンドと合わせて解説する資料を配布しています。




