この会社で「働きたくなる」ためには? 働き方の多様性実現を目指す2社からのメッセージ

ビジュアルコミュニケーションサービスを提供する株式会社ブイキューブは、今年創業20周年を迎えます。同社が提供するウェブ会議システムは、様々な企業に導入され、業務の効率化につながっています。近年、日本でも残業の削減や在宅ワークの推進といった、これまでの働き方を変えようという機運が官民ともに高まっています。
今回、同社の創業20周年を記念して、不動産情報サービスを展開する株式会社LIFULL(以下、ライフル)と対談しました。ライフルは「日本一働きたい会社」を経営理念に掲げています。社員にさまざまな挑戦の機会を与えて社員の自発的成長を促し、その成果を会社の業績に繋げることで経営理念の実現と社員が生き生きと働くことの両立を目指しています。
共通点が多い両社の対談が、働き方に悩む会社員の方々のヒントになれば幸いです。
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
人が働きたくなる理由や理想の働き方の追及がきっかけ
本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。早速ですが、2008年からライフル社は日本一働きたい会社を掲げて、さまざまな取り組みをされていますが、何か課題があってそのような取り組みを始めたのでしょうか。
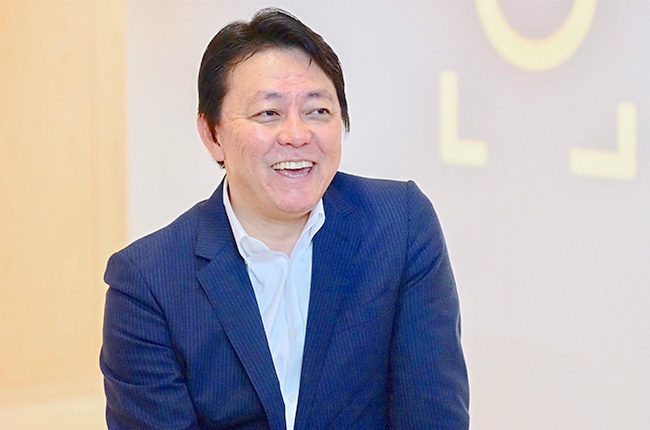
代表取締役社長 井上 高志(いのうえ・たかし)
1968年、東京生まれ。リクルートコスモスやリクルートを経て、1997年に前身の会社を設立。2017年、NEXTからLIFULLへ社名を変更。
1997年、設立。不動産情報ポータルサイトの運営が主力事業。2017年に社名をLIFULLに変更しグローバル企業へと舵を切った。「日本一働きたい会社」を掲げているhttps://lifull.com/
井上氏:2008年から正式なプロジェクトとなるのですが、構想自体は2004年頃から考えていました。日本一働きたい会社を作る、と。課題があったからではなくて、人はどうして働きたくなるのか、という根源的な問題を考えていました。その中で、自分がやりたいことをやっているときが最もパフォーマンスもモチベーションも高い状態になると考えました。
当社では「内発的動機付け」と呼んで大切にしていますが、この動機を邪魔せずに、フォローアップできるような働き方を突き詰めれば、日本一働きがいがあると言われる会社になると考えました。 そのためにどのような制度設計をして、どのように会社の文化を醸成していくのか、を10年以上ずっとやってきました。そのため、課題があったからではなく、人はどうしたら嬉々として自分の好きなことにのめり込んでパフォーマンスを上げることができるのか、というある種の研究を続けてきたと思ってもらってよいと思います。
間下さんはいかがでしょうか。ブイキューブでの取り組みについて、お聞かせ下さい。

株式会社ブイキューブ 代表取締役社長 間下 直晃(ました・なおあき):1977年、東京生まれ。1998年、慶應義塾大学在学中に前身の会社を設立。2002年慶應義塾大学院理工学研究科 修了
1998年10月、大学在学中にブイキューブの前身の会社を創業。情報通信技術を高度に活用することで、テレビ電話でもタイムラグのないシームレスな会話のやりとりを実現するサービスを提供している。2006年、社名を現在のブイキューブに変更。企業のみならず、自治体も含めて60社以上にシステムが導入されている。https://jp.vcube.com/
間下:きっかけが明確にあったわけではありません。ただ、みんなが自分の人生を考えた時に、自分が実現したいことと、自分が何をしていきたいのか、をそれぞれ選ぶ権利があると思います。しかし、日本の高度経済成長時代の名残で、どの働き方がいいのかという選択肢がほとんどなく、これまでに浸透していた画一的な働き方がまだある状況だと思います。
グローバルな社会で他国と比べてみると、日本は非常に残念な働き方が多かったり、自己実現よりも組織に従うことを優先してしまったりする感覚が強いです。これは、2009年ごろから海外、特にアジア展開を始めて、様々な国の働き方を見るにつれて感じ始めたことでした。
私たちは自分たちがやっていることをいかに楽にできるか、やいかにワークスタイルを豊かにするかをテーマに物を作っているので、それをどのように組み合わせれば、自分が理想とする働き方ができるのかを追及しているといった感じです。
ビジョンの共有と会社文化の継承が難しい
ここまでに至る中で、困難を感じたことはありますか。

井上氏:もちろんあります。失敗の実例としては、会社内でビジョンの共有が難しくなってしまったことがありました。短期間で非常に多くの人材を採用していた時期に、会社の文化的な風土ががらっと変わってしまいました。その時期は、あまりに採用者の数が増えたために、最終面接に私が関われず、スキルは高い一方で、ビジョンや理念等の価値観が少し基準から外れた応募者でも採用しがちになっていました。
そうすると少しずつ会社の文化が崩れてきてしまいます。また、過去に1度だけ、減収減益をしたことがあり、そのときに一定数の社員が辞めてしまいました。きっと高い業績を魅力に感じていて、会社の理念にはそれほど共感していなかったのかもしれません。
それ以降、人事において最もこだわっているのは「妥協のない採用」です。ビジョンを共有できていれば、素晴らしい最高のチームを作ることができる、ということを学びました。現在では、妥協のない採用をできるようになっていますし、社員同士が「ライフルは本当にいやな人っていないよね」と会社しているのを聞くとうれしくなります。
間下さんはいかがでしょうか

間下:我々の採用の軸は新卒です。業績が悪いときも毎年ずっと続けています。会社の文化作りの基本は新卒採用だと思っているからです。現在は、成果を含めて非常にいい形になってきていると思います。彼らが脈々と文化を受け継いでほしいです。
ブイキューブ社が導入しているオレンジワークスタイルですが、社員は年齢も違いますしライフステージも様々だと思います。その状況で、ワークスタイルを浸透させるに際しての課題はどのように解決しましたでしょうか。
オレンジワークスタイルは昨年に作りましたが、それは長くいる社員のライフステージが変わったことに対応する必要がでてきたからです。新卒で入社してすぐは、24時間仕事について考えることもできますが、結婚して家族ができるようになると、自分の生活をかえなければいけなくなります。なので、これまでと同じ働き方では会社にいることが難しくなる、ということで、オレンジワークスタイルを作りました。
今は、必要があればすぐにそのワークスタイルを活用する流れが出てきています。さらに活用している様子を周囲の社員が見て、活用しても成果を出して会社もちゃんとそれを評価する流れができてくると、制度の活用を考える社員が増える、という循環が全社的に広がってきたと感じています。我々のようにどこでも働けると提言している会社では、オフィスにいなくても成果を出せるのか、その社員をどう評価するのか、がキーになると思います。その部分がメンバーに分かってもらえるといいサイクルになると思います。
井上さんの会社では、工夫されていることはありますか。
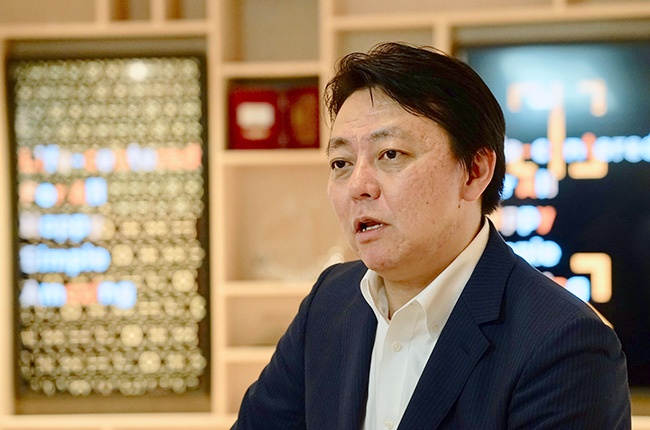
井上氏:日本一働きたい会社は「働きやすさではない」と言い切っています。会社を通して社会を変革する醍醐味ややりがいを重要視しています。ただ、質問いただいたように、働きやすくするための工夫はしています。
その人の能力とパフォーマンスを最大限発揮させるようなバックアップが必要だと感じています。なので、フリーアドレスであるとか家庭環境に合わせてテレワークをしようだとか、選択の自由を増やしているというのはあります。もう少し先の話をしてしまうと、会社に来て働くことそのものが不要になる時代が訪れるだろうと思っています。
そのため、会社は人をつなぎとめるためには、人が集いたくなるコミュニティを作るしかない、能力のある人が、同じチームを組んで一緒にバリューを作り上げたい、と思えるような組織にしないと人が集まらないと思います。
間下:これからは国をまたいで、展開していきますものね。

井上氏:全くその通りだと思います。国も会社と同じで魅力的にしていないと人が集まらないと思います。
間下:それは日本全体の課題として考えないと思います。日本は日本人には居心地がいいですが、外国から見たらそうでもないかもしれない。移民を受け入れの議論が進んでいますが、そもそも来てくれるのかどうかの議論が大事だと思います。
井上氏:特色のあるコミュニティをどう作っていくかという話になってきますね。
労働場所の概念が変わってきている
サテライトオフィスなど、日本国内での取り組みはいかがでしょうか。

間下:場所の概念がどんどん変わっていると感じます。例えば、東京の本社で働いていたとして、都内やその近郊のサテライトオフィスで働いてもよいことにしたとします。そうすると、電車1〜2時間かけて通勤する必要がなくなり、働く環境が改善されて成果を出しやすくなるということがあるかも知れません。また首都圏でのテレワークの他に、地方にサテライトオフィスを設立するということもあります。サテライトをうまく活用すれば、東京の仕事を地方に作ることができると考えています。弊社でも白浜にサテライトと設立したら、東京や大阪から白浜に帰りたかった社員が帰れるようになりました。職住近接なので、オフィスまで徒歩5分、という具合です。東京は便利で面白いですが、生活環境がいいとは言えません。
井上氏:東京は経済成長には適していると思いますが、幸福に直接関与する係数は地方がふんだんにあると思います。
間下:絶対あると思います
規制や慣習を変えるには時間がかかる
井上氏:テクノロジーも人の考え方もどんどん変わってきているのに、ルールや規制が古いままであることが多いです。例えば不動産業界においては、物件の契約は原則対面とされていたり、捺印された書類は5〜10年保管しなさいなど、今の時代にそぐわないことも多いんです。

間下:まさにいま一緒にやっている重要事項説明のオンライン化ですか。
井上氏:そうです、そうです。実現するまで2年半かかりましたが、賃貸物件ではようやくオンラインで重要事項説明とその契約ができるようになりました。売買物件はまだこれからです。ブイキューブさんとともにシステムを開発して、重要事項の説明をオンライン化したら、お客さまは自分の好きな時間で説明を受けられるようになり、足元では月2,000件ほどの利用実績が出ています。お客さまはお店にわざわざ足を運ばなくても良いですし、不動産会社の営業担当者は週末に集中していた契約を平日夜等にもできるようなり、メリットだらけだと思います。
ライフスタイルの変化に合わせて働き方を変える
対談も終盤になりましたが、それぞれの会社が今後、取り組んでいきたいことを教えていただけませんか。

井上氏:社内大学を設置してスキルアップを目指してもらう、など、様々な施策に取り組んでいるので、今後も引き続き、社員が挑戦できる機会は提供したいと思います。社員のライフスタイルの変化で、働き方も変遷するので、週3日だけや土日だけの勤務でもいいとする一方で、1日20時間働きたいです、というような多様性を受け入れるプラットフォームを提供していきたいですね。
人工知能が仕事の80%を奪うという話もありますが、恐怖だと捉えるのではなく、例えば嫌々していた仕事をAIにしてもらって、余った時間を自由に使えるという働き方は魅力的ですよね。

間下:井上さんがおっしゃっていることとかなり近しいので、言うことがほとんどなくなってしまいました(笑)。我々としては、働き方を変えるということは、現在の古い日本企業の体質をどう変えていくか、と同じです。おそらく時間がかかるでしょうし、そのための啓蒙活動を地道にするしかないと思います。
なぜかと言うと、現在の規制は50年〜100年も前に作られたものを基にした規制だと思う。この縛りを変えていかないといけない時間にそろそろ来ていて、産業界からやっていくのは我々の役割のひとつだと考えています。





