表彰式で活用できる!ハイブリッドイベントの開催方法とは?【最新】
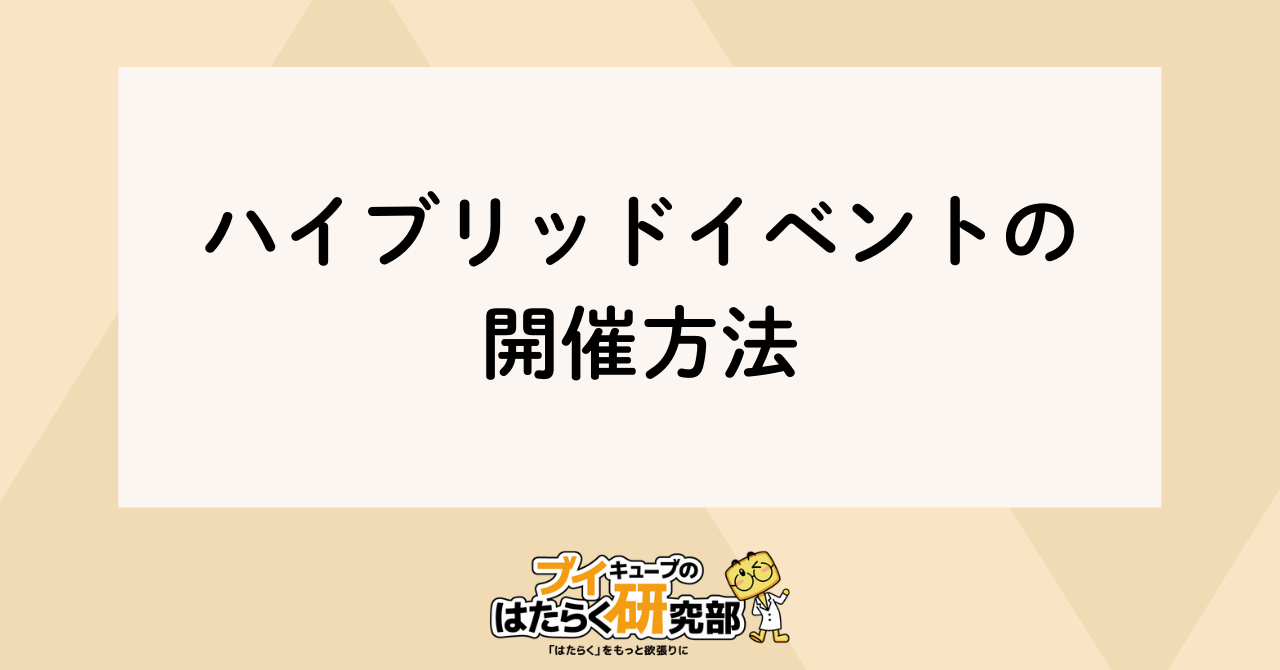
2020年から日本でもコロナの流行が始まり、たくさんの人が今までとは異なる生活をすることになりました。
その中でも大きく変わったことと言えば様々なものがオンライン化したことが挙げられます。
リモートワーク、オンラインでの各種イベント、ウェビナー(ウェブを介したセミナー)も浸透したことによって、オンラインの可能性が世に広く知れ渡りました。
それと同時に、直接対面で話すことの重要性も浮彫りになりました。
「オフラインイベント(対面)」「オンラインイベント」、双方にメリットデメリットがあり、イベントの幹事様は頭を悩ませているのではないでしょうか。
今回は、オンラインと対面双方のメリットを掛け合わせた、「ハイブリッドイベント」の具体的な実施方法をご紹介いたします。
ブイキューブでは、表彰式をはじめとした社内イベントを成功に導くための事前準備や振り返りのポイントをまとめた資料「成功する社内イベントのつくり方ガイド」を提供しています。社内イベントの企画・準備・振り返りにぜひお役立てください。
👉 ブイキューブのイベントの企画・運営・サポートについてはこちら
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
ハイブリッドイベントとは?
ハイブリッドイベントは「オンラインと対面形式を組み合わせた配信形式」です。
対面で行われているイベントの様子をオンライン参加者に配信します。
参加者は「①直接会場での参加」「②オンラインでの参加」を選ぶことができます。
オンライン参加者側からすればテレビ番組のようですが、テレビ番組と大きく違う点は、対面参加者とオンライン参加者(視聴者)の交流が可能となる点です。
支社が全国にまたがっている企業や、感染症の懸念からオンライン参加希望が多い企業など、ハイブリッド形式が選ばれる理由は様々あります。
メリットが多くあることから、今後「ハイブリッドイベントが主流になってくるだろう」と予測されています。
ハイブリッドイベントの実施方法のご紹介
今回は社内表彰式を例にしてご紹介します。
構造さえ掴めれば”社員総会”や”新入社員研修”などにも応用できます。
現場の会場に集める人としては
・司会者
・発表担当
・ノミネート者
・配信スタッフ
・カメラマン
などが挙げられます。
その様子をカメラで撮影し、カメラの映像と、動画用PCから出力したテロップやインサート映像、さらに音響機器やPCからBGMを「スイッチャー」に入力し、合成してひとつの映像にします。
簡単に言うと、「配信用PC1台を通して、映像をオンラインでの参加者の各デバイスにお届けする」という形です。
現場にあるスクリーンでは、Zoomをつなぎます。
「ギャラリービュー」を利用することで、ビデオをオンにしている参加者の表情も伺えます。
直接会うことが難しい今、たくさんの人の笑顔が並んだ画面を見ると、元気が出ますよね。
ノミネートされた現場の方は、スクリーンいっぱいの参加者のみなさんの映像を前に表彰されます。
従来のオフラインの表彰式と同じか、それ以上の「特別感」「高揚感」を得る事ができるのではないでしょうか。
さらに、オンライン参加者からのチャットも見ることができるため、皆さんの反応をリアルタイムで見ることができます。
イベント中、司会者がオンライン参加者のコメントを読み上げる事で、オンライン参加者との一体感が一気に高まります。
(ここは司会者の方の腕の見せ所です)
オンラインの参加者へビデオ通話をつなぐ事も可能なので、現場に居ない人からも動画によるコメントを求めることもできます。
社内イベントの準備について、より詳しく知りたい方向けに「成功する社内イベントのつくり方ガイド」を提供しています。社内イベントの企画・準備・振り返りにぜひお役立てください。
👉 ブイキューブのイベントの企画・運営・サポートについてはこちら
ハイブリッドイベントの工夫例
これまでご紹介したのが、オフラインの現場とオンラインの参加者とをつなぐ「ハイブリッドイベント」の運営の形です。
さらに工夫を凝らすことでさらにイベントのクオリティを上げ、深みを増す事ができます。
最後に
いかがでしたでしょうか。
「ハイブリッドイベント」というと大仰な言葉に聞こえますがこの構造を頭に入れておけば、イベント実施のイメージができるのではないでしょうか。
ハイブリッドによる新しいイベント実施で、コロナ禍の中でも参加者全員で楽しむことができます!こういった段取りには特殊なシステムやノウハウも重要です。
ブイキューブでは社内イベントの運営工数の削減や、費用対効果の可視化などを実現するための社内イベントに特化した運営サポートを提供しています。サービスの詳細は下記よりご覧ください。




