社内イベント後のアンケートは改善サイクルを回すために必須!アンケート実施のポイントや設問例を解説
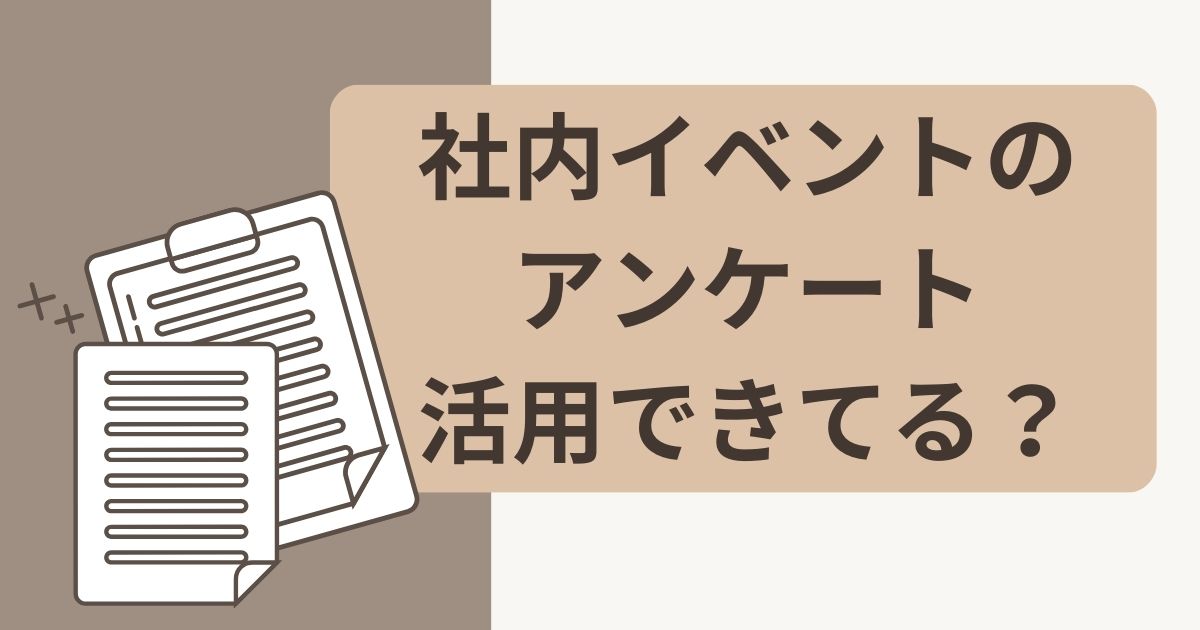
社内イベントの参加者を対象にしたアンケートは、参加者の感想を元に成果測定やイベント改善につなげたり、参加者の希望を元に新企画のアイデアを収集する際に欠かせない施策です。しかしながら、「前回のアンケート結果を見たが、企画立案・効果測定の参考にならなかった」「使えるアンケートを作るにはどうしたらよいのか」などと悩む運営担当者も少なくありません。
株式会社マックスプロデュースが社内イベントに関するカンファレンスの参加者にアンケートを実施したところ、「社内活性化施策に効果が感じられない、または分からない」と回答した視聴者は7割を超えており、成果測定に課題を抱える企業が多い実態がわかります。
そこで今回は、アンケートの重要性について説明した後、効果的なアンケートを作成するためのポイント、イベント種別ごとの設問項目・テンプレートなどの実践的な手法を解説します。効果的なアンケートを実施するためにお役立ててください。
ブイキューブでは、 社内イベントを成功に導くための事前準備や振り返りのポイントをまとめた資料「成功する社内イベントのつくり方ガイド」を提供しています。社内イベントの企画・準備・振り返りにぜひお役立てください。
👉 ブイキューブの社内イベントの企画・運営・サポートについて詳しく見てみる
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
社内イベントのアンケートの重要性
社内イベント後のアンケートは、社内イベントの「Plan(計画)→Do(実行)→Check(測定・評価)→Action(改善)」のPDCAサイクルを回すための「Check(測定・評価)」に相当する施策です。具体的には「効果を測定する」「次回の社内イベントを改善する」「企画立案のアイデアを得る」という3つ役割があります。
社内イベントの振り返りのポイントをまとめた資料は下記からダウンロードいただけます。
👉 ブイキューブの社内イベントの企画・運営・サポートについて詳しく見てみる
効果を測定できる
アンケートで参加者の感想などを集めることにより、目標達成の度合を定量的に測定可能です。特に「非常に不満(1点)、不満(2点)、どちらとも言えない(3点)、満足(4点)、非常に満足(5点)」のように、点数を割り当てる選択式の設問にすると数値化でき、客観的に把握しやすくなります。
この明確な評価段階(スケール)に従ってアンケート調査する方法を「評定尺度法」と呼びます。評定尺度法は、社内イベントへの満足度や印象など、抽象的で測りにくい内容のものを数値化して客観的に分析できることがメリットです。
定期的に催す社内イベントでは毎回同じ設問をして効果測定することにより、過去の社内イベントとの比較しやすくなるでしょう。
次回の社内イベントを改善できる
社内イベントに実際に参加した側からの意見を募ることで、運営側で気付かなかった問題点や課題を発見できるようになります。
例えば、自由形式で社内イベントの良くなかった点について問えば、「毎回同じ内容でマンネリ感がある」「ゲーム企画が個人参加なので一体感がなかった」といった意見が出るかもしれません。イベント自体は成功し、運営側が問題を感じていなくても参加者側からは違った見方をされることはよくあります。
こうした内容をフィードバックし改善していけば、次回の社内イベントはより良いものになるでしょう。
企画立案のアイデアを得る
運営側だけではなく参加者側、また多様な立場の人の意見を聞くことで、次回の企画立案のアイデアやヒントを得られます。そのためには、アンケートの最後には「要望がありましたら、ご自由にお書きください」といった項目があるとよいでしょう。そうすることで、いろいろな人の意見を集められます。
ただし、漠然とアイデアを募集しても意見が出にくく、結局意見が集まらないこともあります。こういった事態を避けるためには、「今後の開催形式はオンライン・オフライン・ハイブリッドのどれを希望しますか?」「参加型のゲームと講演会、どちらに魅力を感じますか?」のように、具体的に質問する方法がおすすめです。
こういった質問方法では新しいアイデア募集にはならないというデメリットはありますが、参加者のニーズを事前にリサーチでき、企画立案の参考にできます。
社内イベントの企画立案のポイントをまとめた資料は下記からダウンロードいただけます。
👉 ブイキューブの社内イベントの企画・運営・サポートについて詳しく見てみる
次のイベントに活用できる!社内イベントのアンケートの条件
アンケートの結果を社内イベントに活用できていない場合は、設問項目や質問の仕方などに問題があるのかもしれません。ここでは効果的なアンケートにするための条件、ポイントを解説します。
アンケートの実施目的を明確にしておく
アンケート内容を作成する前に、まず実施目的を明確にしておきましょう。アンケートを作成していると、聞きたい項目がどんどん増えてしまうことがあります。しかし、あまりに膨大な設問量では、回答者が途中で答えるのを止めてしまうかもしれません。
どうしても聞いておきたい大事な項目は何か明確にするためにも、まずは目的を設定し、それに合ったアンケートを考えるようにしたほうがよいでしょう。
社内イベントの目的はどう作成する?
「社内イベントの目的はしっかり定義すべき!その効果や成功のコツとは」で詳しく解説しています。
回答率が上がる工夫がされている
社内イベントの参加者にとって、アンケートへの回答は基本的に面倒なものです。負担が大きくなれば、アンケートの回答率が下がる傾向があります。参加者の負担に配慮したアンケート内容になっているか、以下の点には気をつけましょう。
- 設問量
- 回答形式
- アンケートのタイミング
設問量
まず確認したいのが設問量です。一般的にアンケートの回答時間は5分以内で、約15個以内の簡単な質問で構成するとよいとされています。あまりに設問が多く時間がかかるものだと、回答者は途中で回答をやめてしまう、適当な回答をしてしまう、といったことが起こり得ます。
詳しく調査したい場合もあるでしょうが、長くても10~15分で回答できる内容にするとよいでしょう。それ以上は回答者の負担になってしまいます。また、回答にかかる目安時間をアンケートの冒頭に書いておくと、見通しがつくためよいでしょう。
回答形式
回答形式の選択も重要です。「社内イベントの開催形式について、どう思いますか?」といったオープン・クエスチョンは、自分の意見を文章にしなければならないため、回答負担が大きくなります。重要な内容に絞って質問したほうがよいでしょう。
一方、「はい、いいえ」「満足・不満足・どちらでもない」などで回答してもらう選択式のクローズド・クエスチョンは、すぐに回答できることから回答負担は大きくありません。例えば、アイデアを募るような場合も、2~3の案を提示して選択してもらい、それ以外の案がある人は自由回答してもらうようにする、といった方法にすると回答しやすくなります。
アンケートのタイミング
アンケートのタイミングについても考慮が必要です。タイミングは、社内イベントの記憶が鮮明なイベント直後が理想的です。参加者へのお礼メールにアンケートを添付して回答を促したり、イベントの帰り際に回答してもらう段取りにしておいたりすると、回答率を高められるでしょう。
本音を引き出す工夫がされている
アンケートによって率直な意見、感想を聞き出せなければ、成果測定や改善などにはあまり役に立ちません。本音を引き出したいときのアンケート形式と心理的なバイアスについて注意点について解説します。
匿名方式か記名方式か
アンケートから参加者の本音を引き出したいときは、匿名方式が向いています。記名方式の場合、参加者が「人事評価の参考にされるのではないか」「プライバシーが保護されないのではないか」などと気にする場合があるからです。その結果、企業側への忖度、遠慮が働いてポジティブな回答に偏ったり、無難な回答を選んだりして、有益な情報が得られない場合があります。
どうしても参加者の属性などの情報を集めたい際は、「年齢」「性別」「部署」「勤続年数」などを問う方法もよい方法です。こうすればプライバシーに配慮しつつ、参加者の属性を加味した分析が可能となります。
心理的なバイアスが生じないように注意する
客観的でフラットな意見を得るためには、バイアスを生じさせる要素がないかをチェックしておきましょう。
例えば、「社内イベントのコストを抑えたいと考えている」と事前にアナウンスしてからアンケートを募ると、「アンカリング」のバイアスがかかる恐れがあります。
アンカリングとは、先に与えた情報が全体の方向性を決めてしまい、判断を歪めてしまうバイアスです。この場合、多くの設問に対して金銭的な基準で回答する傾向になり、自由な意見が出にくく現実離れした結果になる可能性があるため注意が必要です。
また、設問の順番によって「プライミング」のバイアスがかかる可能性もあります。プライミングとは、例えば「社内イベントにオンラインで参加したいか?」と質問した後に、「社内イベントの開催形式はどれがよいか?」と問うと、前の内容が影響して「オンライン開催」と回答する割合が増えるバイアスです。
このように意図せず回答を誘導していないかどうか、事前に確認しておきましょう。
社内イベントの振り返りのポイントをまとめた資料を下記からダウンロードいただけます。
👉 ブイキューブの社内イベントの企画・運営・サポートについて詳しく見てみる
イベント種別の設問項目・テンプレートを紹介
ここからはアンケート作成に役立つアンケート項目・テンプレートを紹介します。典型的な設問をピックアップして紹介していますので、自社の調査目的に合わせてアレンジできるでしょう。
1.懇親会/交流イベント
懇親会/交流イベントは、参加者が楽しめたかどうか、他者と交流できたかどうかが重要なポイントです。参加者の反応を定量的、客観的に測定するには、「満足した・不満足」といった対立的な形容詞の対を用いて3~7段階で回答してもらう「SD法」の設問を中心に構成するとよいでしょう。
【例】
|
設問 |
回答欄 |
|
社内イベントを楽しめましたか? |
非常に楽しかった・やや楽しかった・どちらとも言えない・ややつまらなかった・非常につまらなかった |
|
他の参加者とのコミュニケーションを取れましたか? |
よく取れた・やや取れた・どちらとも言えない・あまり取れなかった・全く取れなかった |
|
司会・運営はスムーズでしたか? |
非常に当てはまる・やや当てはまる・どちらとも言えない・やや当てはまらない・全く当てはまらない |
|
次回イベントも参加したいと思いますか? |
非常に参加したい・やや参加したい・どちらとも言えない・やや参加したくない・全く参加したくない |
2.スキル向上/トレーニングイベント
スキル向上/トレーニングイベントのアンケートで重要なのは、アンケートと理解度テストを明確に区別することです。両者を混同すると、アンケートの設問数が増える上に、イベントの効果と参加者の理解度の測定が混ざってしまうため、どちらも中途半端になってしまいます。
そのため、イベントで学んだことが身についているのかチェックするための理解度テストが必要な場合、アンケートとは別途作成するようにしましょう。アンケートでは、以下のように「参加者が有意義に感じたか」「内容に満足できたか」など、イベント内容を問う設問を中心に構成します。
【例】
|
設問 |
回答欄 |
|
研修内容に満足できましたか? |
非常に満足した・やや満足した・どちらでもない・やや不満足・非常に不満足 |
|
イベントスタッフは親しみやすかったですか? |
親しみやすい・どちらでもない・親しみにくい |
|
トレーニング時間についてどう思いましたか? |
ちょうど良い・長すぎる・短すぎる |
|
本イベントの参加を同僚に勧めたいですか? |
勧めたい・どちらでもない・勧めない |
|
本イベントで良かった点・悪かった点を教えてください |
自由形式で回答 |
|
本イベントの講師について意見があれば教えてください |
自由形式で回答 |
3.チームビルディング/協力イベント
社内イベントにおけるチームビルディング/協力イベントでは、さまざまな立場の人が共同作業をするのが一般的です。立場によって、イベントに対する反応が大きく変わる場合があるため、匿名回答の場合は参加者属性を聞き取っておくと、分析しやすくなります。そのため、以下のように年齢や部署を問う設問を最初に入れておくと効果的です。
【例】
|
設問 |
回答欄 |
|
あなたの年齢を教えてください |
20代・30代・40代・50代・60代以上 |
|
あなたの所属部署を教えてください |
自由形式で回答 |
|
チームビルディングに取り組んだ経験はありましたか? |
ある・ない |
|
協力イベントに意欲的に取り組めましたか? |
はい・いいえ・どちらでもない |
|
講義時間は適切でしたか? |
ちょうど良い・長すぎる・短すぎる |
|
このイベントで得た経験を、今後の仕事にどう活かしたいですか? |
自由形式で回答 |
4.表彰/感謝のイベント
表彰/感謝のイベントは、社員のモチベーション向上や成果に対して正当な評価を与えることなどを目的に開催されます。したがって、会社への貢献意欲や愛着心などを表す「従業員エンゲージメント」を測定できる設問を中心に構成するのが一般的です。こういった設問でアンケートをとると、イベントが仕事に効果をもたらしているかどうかを把握できます。
【例】
|
設問 |
回答欄 |
|
本イベントは仕事へのモチベーションアップにつながっていますか? |
非常にそう思う・ややそう思う・どちらでもない・あまり思わない・全く思わない |
|
本イベントで会社への信頼・親和度が高まりましたか? |
非常にそう思う・ややそう思う・どちらでもない・あまり思わない・全く思わない |
|
ナレッジ共有(※)に役立っていると思いますか? (※)業務に必要な知識やノウハウなどを社員同士で共有すること |
非常にそう思う・ややそう思う・どちらでもない・あまり思わない・全く思わない |
5.社内戦略/ビジョン共有イベント
社内戦略/ビジョン共有イベントは、経営者が企業理念やビジョン、達成目標を語ったり、社員同士が会社の進むべき方向性について議論したりするためのイベントです。「社内総会」「キックオフ」と呼ばれる場合もあります。
株式会社オージャストの「社員総会のマンネリ化に関する実態調査」によると、イベント開催の目的は「生産性向上(57.3%)」「モチベーションの向上(55.5%)」「ロイヤリティ向上(50.9%)」がトップ3(複数回答可)であるため、これらに関する設問を中心に構成するとよいでしょう。
また、同調査によると、約9割が社員総会にマンネリ化を感じているという結果も出ているので、マンネリ化についての設問も含めておくことがおすすめです。
【例】
|
設問 |
回答欄 |
|
企業理念やビジョンに共感し、その達成に貢献したいと思いますか? |
非常にそう思う・ややそう思う・どちらでもない・あまり思わない・全く思わない |
|
会社の業績(収益性、成長性など)に満足していますか? |
非常に満足している・やや満足している・どちらでもない・やや不満足・非常に不満足 |
|
本イベントで自由に自分の考えやアイデアを言える雰囲気があると思いますか? |
非常にそう思う・ややそう思う・どちらでもない・あまり思わない・全く思わない |
|
社員総会に対してマンネリ化を感じていますか? |
非常にそう思う・ややそう思う・どちらでもない・あまり思わない・全く思わない |
|
「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答した方にお聞きします。あなたがマンネリ化を感じる理由を教えてください。 |
自由形式で回答 |
アンケートは効果的な社内イベントを企画するために重要な施策!
社内イベント後に実施するアンケート調査は、成果測定やイベントの改善、新たな企画立案にとって重要な施策です。アンケートから参加者の本音を引き出し、有益な分析につなげていきましょう。
参加者の要望や不満は把握できたものの、具体的な企画に落とし込めない場合は、企画段階から専門的な知見を持った業者に相談するのも有効な方法です。
例えば、初めてオンライン形式の社内イベントを開催する場合は、通信トラブルやインフラ整備などで不安になるものですが、専門的なノウハウを持った業者に依頼すれば、リアルなイベントを安定したプラットフォームで運営できます。
ブイキューブは、20年も前からオンラインコミュニケーションシステムを開発し、提供してきました。メタバースからハイブリッドまで、企業のためのイベント配信をトータルサポートできます。
「数万人規模の大規模イベントを開きたい」「双方向コミュニケーションを充実させたい」「3DCGメタバースによる次世代型イベントを開催したい」などのゴールに合わせて、企画段階から多様なサービスを提供していますので、ぜひお気軽にご相談ください。
ブイキューブのインナーイベントパッケージ




