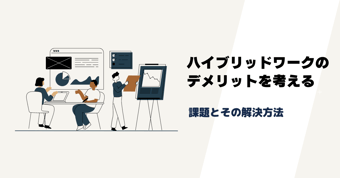今後のリモートワークはどうなる?検討材料や各社の対応とともに解説

コロナ禍により一気に普及が進んだリモートワーク。一方で、アフターコロナの時代もリモートワークを続けるべきか悩んでいる経営者の方や人事担当者の方は多いのではないでしょうか。
本記事では、アフターコロナ時代のリモートワークの動向を大手各社の対応をもとに解説しています。継続を検討する際の参考にしてみてください。
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
リモートワークは今後も続く?
今後のリモートワークの動向について解説します。
2022年1月現在の新型コロナウイルス感染状況を鑑みても、2022年度にリモートワークを実施する企業数は前年と比較してほぼ横ばいに推移することが予想されます。
加えて、ワクチンの接種率の上昇などに伴い、ある程度のコロナ禍の収束が見られた場合も、2025年までは働き方改革の一環として多くの企業がリモートワークを継続する流れが想定されています。
また、9割近くの企業がリモートワークを継続する意向を示している調査結果もあります。その要因には、リモートワークが生産性の観点で業務に影響を及ぼさなかった点が大きく関係しています。しかし、非対面でのコミュニケーションゆえに、7割の企業が部下のマネジメントに関して課題を感じているのも現状です。
リモートワークを続けるかの検討材料
リモートワークの継続を検討する際の傾向として、十分にリモートワークのメリットを享受できた企業ほど継続する意向を示しています。一方でリモートワークにはメリットと同時にデメリットもあり、オフラインならではの良さも軽視できません。これらの要素を、比較しつつ検討してみましょう。
リモートワークにはさまざまなメリットがあります。たとえば、遠隔地でも働けるため全国各地から人材確保が可能です。加えて、通勤費やオフィスの家賃などのコスト削減や、従業員のワークライフバランスの充実、生産性の向上が期待できます。
リモートワークのメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
担当者が押さえておくべきテレワークの5つのメリットを事例付きで解説
関連記事「担当者が押さえておくべきテレワークの5つのメリットを事例付きで解説」では、メリットを詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
一方で、リモートワークにはデメリットもあります。たとえば、セキュリティ問題や、非対面ゆえのコミュニケーション不足などが広く知られています。他にも、組織としての一体感が薄れることにより部下のマネジメントが難しい点や、目に見えない場所での働きを評価する制度が整備しづらい点もデメリットといえるでしょう。
リモートワークのデメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
テレワークのデメリットとは?働き方改革を成功させるポイントと成功事例
さらに詳しくテレワークについて知りたい方は、関連記事「テレワークのデメリットとは?働き方改革を成功させるポイントと成功事例」でもメリットを詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
しかし、これらの問題は就業規則の改定や対策ツールの導入によって解決が可能です。リモートワークを導入するうえで、新しい働き方に合わせたルールづくりと、コミュニケーションや労務管理、マネジメントを効率化する業務ツールは必要不可欠です。
リモートワークで生じる問題を解決する方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【完全ガイド】テレワークに必要なルールと就業規則の制定・改訂手順とは
さらに詳しく知りたい方は、関連記事「【完全ガイド】テレワークに必要なルールと就業規則の制定・改訂手順とは」でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
リモートワークのデメリットは解決可能ではあるものの、もちろんオフラインでの働き方ならではの良さはあります。そこで提案したいのが、ハイブリット型の働き方です。
ハイブリッド型とは?
ハイブリット型とは、リモートワークだけでなくオフラインでの働き方も考慮した、双方の良さを取り入れる働き方のこと。アフターコロナの働き方において、ハイブリッド型をとりいれる意向を示している企業も多く存在します。
企業の今後のリモートワークに対する対応
アフターコロナにおける大手各社のリモートワークへの対応を紹介します。
Googleはハイブリッド型を導入する意向を明らかにしています。もともとは無料の社内食堂やジムなどのオフィスワークを前提とした働きやすさを売りにしていたGoogleですが、今後は働き方の選択肢も増やしていく方向性を示しています。
参考:グーグルのピチャイCEO、週3日の出社を推奨…「バランスが取れている」 | Business Insider Japan
Meta
Facebookを運営するMetaは大々的にリモートワークを推進する意向を示しています。全世界に6万人いる社員の5割を今後10年かけてリモート勤務にできるようにするなど積極的な試みを実施しています。
参考:フェイスブック、リモート勤務可能な全社員にパンデミック後も認める方針 - BBCニュース
Amazon
Amazonはアフターコロナ時代の働き方において、オフィス出社を社員に要請せず、チームごとの判断に委ねる意向を示しています。ただし、社員は1日以内にオフィスに行ける場所にいることが望ましいとしています。
参考:アマゾン、オフィス復帰計画を中止…在宅勤務の可否はチームの判断に委ねる | Business Insider Japan
Twitterはアフターコロナの時代において、業務の性質上出社が義務付けられている社員を除き、希望する社員はリモートワークを永続的に継続できると発表しています。
出典:COVID-19の流行期間中、社員やパートナーの安全を守るための取り組み
Yahoo!
Yahoo!は2014年より段階的にリモートワークの導入を推進してきましたが、コロナ禍を受けて2020年10月より無期限リモートワークをスタートさせています。リモート環境での生産性についての社内アンケートでは、92.6%の社員がリモート環境においても生産性への影響がなかったもしくは向上したという調査結果もあります。
出典:ヤフー、10月より無制限リモートワーク運用開始 時間と場所に捉われない新しい働き方へ
富士通
テレワークをベースとしながらも、オフィスでの対面のコミュニケーションを組み合わせた「Hybrid Work(ハイブリッドワーク)」を進めます。オフィスを仕事場ではなく、そこでしかできない体験を提供する場に転換。リアルでのコミュニケーションを通じたコラボレーションをより多く生み出すような「多様な従業員が集い・働き・学び・交わる場」として活用します。
出典:一人ひとりのWell-beingに向き合うDX企業としての働き方へ「Work Life Shift」の進化S
Sansan
リモートワークを併用しつつ、オフィスを基点とする働き方に切り替えます。オフィスでの対面のコミュニケーションをベースとした働き方としながらも、出社頻度を自ら選択できる勤務形態を制定しています。
出典:Sansan、オフィスとリモートワーク掛け合わせた新勤務形態開始 「マルチプロダクト体制」へ移行発表
ドワンゴ
基本は在宅勤務で、必要に応じて出社する勤務形態に全社で移行します。2020年の2月から行っていた全従業員の在宅勤務の結果、生産性が落ちなかったことなどから今回の方針につながっています。
出典:ドワンゴ、アフターコロナも基本在宅勤務に 出社と在宅のバランス探る - ITmedia NEWS
まとめ
リモートワークはコロナ禍を経てさまざまな企業に取り入れられ、多くの人々にとってスタンダードな働き方のひとつとして認識されるようになりました。アフターコロナの時代においてもリモートワークを継続したいと考えている人は多く、継続のためにはツールなどを積極的に導入し、業務の最適化を図る必要があります。
また、リモートワークとオフラインの双方の良さを取り入れたハイブリット型のリモートワークを活用することで、アフターコロナ時代の業務に柔軟に対応することが可能です。