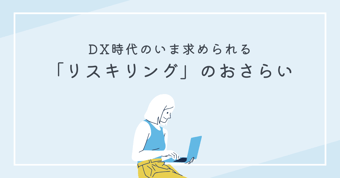オンライン授業のやり方を徹底解説|基本~おすすめツールまで紹介

「オンライン授業を取り入れたものの、今のやり方でよいのか不安」
「オンライン授業を生徒たちにとってより学びやすい場にしたい」
こうした思いをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、急速にオンライン授業が普及しました。
多くの教育現場に急いで取り入れられた反面、オンライン授業のやり方をゆっくり見直す機会は得にくかったといえます。
そこで本記事では、オンライン授業のやり方について基本から各手法のメリットとデメリット、おすすめツールまでを徹底解説します。
ぜひ、よりスムーズで学習効果の高いオンライン授業の実現にお役立てください。
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
オンライン授業とは
オンライン授業とは、インターネット回線を通して遠隔で行う、時間や場所にとらわれない教育手段のひとつです。一般的にパソコンやタブレットなどを使用して受講します。
オンライン授業の手法はおもに3つあります。リアルタイムで授業を中継する「Live配信」、あらかじめ録画した授業を用いる「オンデマンド配信」、Liveとオンデマンドに対面を組み合わせた「ハイブリット」です。
以下の表にて3つの手法をそれぞれ解説します。
|
方法 |
Live配信 |
オンデマンド配信 |
ハイブリット |
|
実施形態 |
授業をリアルタイムでオンライン配信する形態 |
事前に録画した授業をオンラインで配信する形態 |
Live配信やオンデマンド配信に加え、対面までふくめて実施する形態 |
|
メリット |
・画面上でお互いの顔を確認でき、一体感が生まれやすい ・理解度を確認したり、必要に応じて補足したりと臨機応変な進行が可能 ・質疑応答が可能 ・チャット機能や資料の画面共有機能を活用できる ・大人数で同時にオンライン授業を行える |
・自分のペースで好きな時間に学習できる ・動画の巻き戻しを使って分からない部分を繰り返し視聴できる ・講師側は、取り直しや編集により内容を整えたものを配信できる |
・対面、Live配信、オンデマンド配信を組み合わせて行える ・受講者は、対面かオンライン配信かなどを選択できる ・Live配信と対面ともに空間を共有できる |
|
デメリット |
・授業進行のスムーズさが参加者全員の通信環境に左右される |
・その場で質疑応答ができない ・監視者がいないため、集中力が持続しにくい ・別途、受講状況を管理する必要がある |
・対面の受講者に意識が向き、オンラインの受講者への対応が難しい ・黒板を映して授業をするか、画面に向かって授業をするかの選択が困難 |
|
活用事例 |
・オンライン英会話、コミュニケーションをとりながら行う授業 ・小・中学校など進捗状況の把握が必要な授業 |
・塾や予備校の授業 ・企業の社員教育用e-ラーニング ・出席をとる必要のない大学の授業 |
・大学の授業(大人数での授業が難しい場合に、対面とLive配信に分割、希望者のみ対面などの処置が可能) ・社内研修(対面とオンデマンド配信の組み合わせなど) |
オンライン授業を始める前の準備
オンライン授業をスムーズに行うためには、事前準備が大切です。
ここではオンライン授業を行う前に必要な準備について、「授業を行う側」と「授業を受ける側」それぞれの観点から解説します。
授業を行う側
オンライン授業を行う側は、大きく分けて2点「通信環境・ツールの準備」と「授業内容の準備」を整えておく必要があります。
通信環境・ツールの準備
オンライン授業を行うための通信環境およびツールの準備は以下の通りです。
・通信環境の整備
安定した映像や音声を受講生に届けるためには、通信環境が重要です。
一般的には、有線LANの方が無線LAN(Wi-Fi)に比べて安定性が高いといえます。とくにオンラインの人数が多い、動画を配信したい、大容量の資料を配布したいなどの場合は有線LANにしておくと安心です。有線LANのなかでも大容量で通信速度が高く、安定性のあるブロードバンド回線の光回線の使用がおすすめです。
・配信機器の準備
パソコン・モニター・カメラ・マイクなど、配信するための各機器をそろえる必要があります。
とくにマイクは、聞き取りやすさが授業への集中度合いに直結するため、慎重に選びましょう。例えば、オンライン授業中に移動や動作が多い場合は、ワイヤレスタイプのマイクがおすすめです。ただ、音質や安定性はワイヤレスタイプよりも有線タイプが優れているので、授業内容に応じて選択するのがよいでしょう。
また、ハイブリットのオンライン授業で対面受講者の声もひろいたい場合などは、マイクとスピーカーが一体となっているマイクスピーカーをおすすめします。単純にモニターのスピーカーから音を出して、別でマイクをつける方法ではハウリングしやすいためです。
・Web会議ツールの選定・ダウンロード
オンライン授業を行うためには、「Zoom」や「Google Meet」などのWeb会議ツールをダウンロードしておく必要があります。
無償版もありますが時間制限(Zoomは40分、Google Meetは60分)や、録画機能の利用可否(Zoom は可、Google Meetは無償版では不可)の違いがあるため、オンライン授業の実施方法によって使い分けが必要です。
授業内容の準備
オンライン授業のを成功させるためには、詳細内容を決めていく必要があります。具体的には以下の通りです。
・オンライン授業の方法を決定
Live配信・オンデマンド配信・ハイブリットのいずれの方法で行うかを決定します。目的に応じて適した方法が異なるため、それぞれのメリットとデメリットを考慮して選択しましょう。
例えば、「受講者はやむなく全員自宅からの参加だが、リアルタイムでの質疑応答を可能にしたいからLive配信」といった要領です。
・オンライン授業の日程と参加URLの通知
オンライン授業を行う日程を決め、会議のURLとあわせて受講者に通知しましょう。
とりわけ招待用URLは、「Zoom」や「Google Meet」などのツール上で作成します。
作成したURLは、テキストとしてコピー&ペーストで扱えます。メールで共有や共用しているカレンダー機能で共有、学校のウェブサイトでの共有など、自由な通知方法を選択可能です。
・オンライン授業のマニュアル作成
オンライン授業に慣れていない受講者もいるため、ツールのダウンロード方法や基本的な使い方などを分かりやすくまとめたマニュアルを作成しましょう。
また、出席確認方法や課題の提出方法などのルールをあらかじめマニュアルにも掲載しておくとスムーズです。
・オンライン授業で使う資料の共有
オンライン授業の当日に用いる資料は事前にPDFにして共有しておくとよいでしょう。受講者は必要に応じて、コピーしたものを手元に用意して受講できます。
配布時のファイル形式は、基本的には改ざんや誤った編集を防止するPDF形式がおすすめですが、書き込みやワーク等がある場合はWordやExcelなどもよいでしょう。ただし、受講生側のパソコンで閲覧ができることが前提です。
授業を受ける側
オンライン授業は双方向の通信のため、授業を受ける側(受講者)も一定の準備を求められます。具体的には以下5点です。
・通信環境の整備
安定した映像や音声を受け取るためには、通信環境が重要です。
有線LANの方が無線LAN(Wi-Fi)に比べて安定性が高いため、普段はWi-Fiを利用しているとしても可能であれば有線での接続をおすすめします。
有線化が難しい場合は、家庭内ではあれば家族の協力を得て、授業時間は他でのWi-Fi利用を控えてもらうなどでも一定の効果が期待できます。
もちろん無線LANであっても問題なく受講できる場合もありますが、念のため接続テストをしておくと安心です。
・パソコンorタブレット(orスマートフォン)
基本的には、パソコン・タブレット・スマートフォンどの端末でも受講可能です。ただし、スライドや板書などをみる場合はパソコンやタブレットがおすすめです。
また、スマートフォンの場合はWi-Fi接続を利用しましょう。携帯電話回線で接続するとプラン次第では利用上限に達するなどのデメリットが発生してしまいます。
・受講環境の整備
雑音が入りくいスペースや、長時間使っても疲れにくい自分に合った机・イスなどを確保することで、オンライン授業への集中力が増します。
・Web会議ツールのダウンロード、操作方法の確認
オンライン授業の受講のためには、専用のWeb会議ツールのダウンロードが必要な場合があります。講師側からの通知をよく確認しましょう。あわせて、ツール基本的な操作方法を確認しておくことでスムーズな受講が可能です。
・オンライン授業のマニュアル・ルールの確認
オンライン授業は出席や課題提出など対面授業と異なるため、講師側からの通知やマニュアルを事前に確認しておきましょう。
オンライン授業の進め方
オンライン授業の本番当日、事前準備をしっかりと行っていれば心配いりません。ここでは、オンライン授業の方法別に進め方を紹介します。
Live配信
Live配信は以下の手順で進めましょう。
1.事前に通知している少し前の時間にURLへアクセス
接続に問題がないかの確認と、早めに参加する受講者をうけ入れるため、定刻よりも10~20分前にはアクセスしておきましょう。
2.受講者名の確認を行い、参加を許可
順次アクセスしてくる受講者の名前を確認し、参加を許可します。
参加URLの取り扱いに気をつけていれば部外者が入ることは稀ですが、ときどき表示名に誤りがあったり、ニックネームにしていたりといったケースがあるため注意が必要です。
3.出席を確認
受講者の出席状況を確認します。参加者一覧をスクリーンショットでとっておく手段もあります。
4.パワーポイントなどを共有しながら授業を開始
事前に準備しておいた資料を共有しながら授業を進めます。表示する資料を変更するたび、問題なく映し出されているかを確認しましょう。
5.課題提出や次の授業をアナウンス
課題用ファイルを配布したい場合は、ツール内のチャット機能を利用できます。授業終了後にメールなどで別途案内する方法もあります。
詳細なやり方はこちらで詳しく紹介しいますので、ぜひあわせてご覧ください
Zoomについては「初心者必見!Zoomの使い方、ミーティング開催・操作方法を解説」、Google Meetについては「Google Meetの特徴を他のWeb会議ツールと徹底比較!使い方も解説」で詳しく紹介しています。
オンデマンド配信
オンデマンド配信には、「Zoom」や「Google Meet」などのWeb会議ツールを用いるパターンと、授業を風景をカメラで録画するパターンがあります。以下でそれぞれの手順を紹介します。
Web会議ツール上で行う場合

Web会議ツールを用いる場合は以下の手順です。授業後に録画や保存ができていなかったという事態を避けるため、一度1~4までの手順を1分程度の録画で試しておきましょう。
1.Web会議ツールを立ち上げる
「Zoom」や「Google Meet」などのWeb会議ツールを起動します。なお、外付けカメラを用いれば、授業風景など広い範囲の撮影も可能です。
2.授業の資料を共有する
事前に作成しておいた授業用の資料(PowerPointやWordなど)を共有状態にしておきます。授業のタイトルや日付、開始~終了予定時間を表示しておくと受講者に親切です。
3.画面録画をスタートさせ、授業を開始する
準備が整ってから録画をスタートさせましょう。必要に応じて録画の一時停止なども可能です。
4.録画を終了し、保存先を確認
予定していた内容を終えたら、録画終了ボタンをクリックします。所定の場所へ保存されるため録画できているかを確認しましょう。
5.アップロードして共有
例えば、YouTubeやGoogleドライブ、学校のウェブサイトなどにアップロードして受講者に、リンク先を伝えて共有します。
6.授業の受講状況を確認
アップロードした動画へのアクセス履歴や授業の感想、課題などで受講状況を確認します。
詳細なやり方はこちらで詳しく紹介しいますので、ぜひあわせてご覧ください
Zoomについては「Zoomの録画機能の活用方法を解説!やっておくと便利な設定やデータ管理の方法を紹介」、Google Meetについては「Google MeetでWeb会議は録画できる!録画や共有の方法も紹介」で詳しく紹介しています。
授業風景を撮る場合

ビデオ(カメラ)を設置して授業を撮影します。パソコンのカメラアプリを利用する場合は、外付けカメラを用いて広範囲の撮影を可能にしましょう。
1.ビデオ(カメラ)を設置
どのような角度や範囲で撮影するかを決めてビデオ(カメラ)を設置します。授業中に人の移動がある場合は、引っかかって位置がずれたり倒れたりしないよう配置や配線には注意が必要です。
2.音声や画角を確認
試し録画により、音声に問題がないか、必要な範囲が見切れないかを確認しましょう。
3.授業を撮影
準備が整い次第、授業の撮影を開始します。とくに動きを取り入れる場合や物を提示する場合には、見切れないようにしましょう。録画終了後は必要に応じて編集を行います。
4.アップロードして共有
例えば、YouTubeやGoogleドライブ、学校のウェブサイトなどにアップロードして受講者に、リンク先を伝えて共有します。
5.授業の出席を確認
アップロードした動画へのアクセス履歴や授業の感想、課題などで受講状況を確認します。
ハイブリット
対面授業とLive配信およびオンデマンド配信を組み合わせます。それぞれの基本手順は変わらないため、あとは受講者の視点から考えることでよりスムーズに授業を行えるでしょう。
対面とLive配信の場合は、オンラインとオフラインそれぞれの受講者同士の声が聞こえ合うように、据え置きのマイクスピーカーを使用するとよいでしょう。授業に一体感が生まれる効果も期待できます。
対面とオンデマンド配信の場合は、対面の受講者からの質問や回答も録画に残す必要があります。講師がピンマイクを使用しており、対面受講者の音声をひろえない場合は、講師が発言を復唱するなど工夫しましょう。
おすすめのWeb会議用マイクスピーカー8選|商品選びのポイントとは?
Web会議マイクスピーカーについては、「おすすめのWeb会議用マイクスピーカー8選|商品選びのポイントとは?」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてお読みください。
オンライン授業をする際の注意点
オンライン授業を行う際の注意点を4点解説します。
・事前準備を徹底する
オンライン授業は対面授業以上に入念な準備が必要です。
具体的には、サインインや録画の方法はもちろん、画面共有や受講者を強制ミュートにする方法など事前に操作方法を確認しておきましょう。受講者にもやり方を伝えておくことで当日の進行がスムーズになります。
詳細なやり方はこちらで詳しく紹介しいますので、ぜひあわせてご覧ください
Zoomについては「初心者必見!Zoomの使い方、ミーティング開催・操作方法を解説」、Google Meetについては「Google Meetの特徴を他のWeb会議ツールと徹底比較!使い方も解説」で詳しく紹介しています。
・接続テストやシミュレーションを行う
受講者数名や他の講師に協力を依頼して、本番に近い環境での接続テストやシミュレーションを行いましょう。
テストを行うことで想定外の問題を把握し、事前に対処できます。とくにハウリングなど音響まわりのテストは入念に行うことをおすすめします。
・回線トラブルやその他トラブルでで受講できなかった場合のフォローを考えておく
回線トラブルで受講できなかった場合は、録画した動画のURLを未受講者へ案内します。
ただし、URLが外部に漏れないよう十分に注意し、案内の際にも注意喚起を行います。動画に視聴期限を設けることもおすすめです。
・出席や課題など成績に関わるルールを定めて提示しておく
オンライン授業は対面授業と比較すると、受講への強制力は低いといえます。一方では回線トラブルにより欠席せざるをえない場合もあります。
そのため、成績に関わる出席や課題などのルールは明確に設定しておき、あらかじめ受講者へ提示しておきましょう。例えば、「いかなる理由であっても欠席の場合は録画視聴および追加課題を科し、提出をもって出席と同等にあつかう」のようにです。
オンライン授業におすすめのツール
オンライン授業に用いるWeb会議ツールでとくにおすすめのツールを紹介します。
Zoom
「Zoom」は全世界で3億人以上が使用するWeb会議ツールで、オンライン授業にも適しています。「Zoom ミーティング」は、受講者をミュートにして講師の音声のみを届けることが可能です。また、チャットでの質問受付や、アンケートも取れ、スムーズに授業を進められます。
「ブレイクアウトルーム」を用いれば、少人数グループに分かれてコミュニケーションを行えます。受講者同士がディスカッションを行う授業にピッタリです。講師は各ルームを自由に出入りできます。
「Zoom」上で行った授業を画面録画しておき、オンデマンド配信も可能です。なお無償版であっても40分はオンライン授業を行える上、録画(ローカル保存のみ)もできます。カレンダーとも連携できるため、オンデマンド配信に役立ちます。
ただし、Live配信の場合は40分制限がネックとなる場合が多いため、有償版がおすすめです。
Zoomのビジネス利用なら有料プラン!各プランの料金や特徴を解説
Zoomの有料プランの詳細については、「Zoomのビジネス利用なら有料プラン!各プランの料金や特徴を解説」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてお読みください。
Google Meet
「Google Meet」はGoogleが提供しているWeb会議ツールで、オンライン授業にも活用されています。
「Google Meet」でも受講者をミュートにして講師の音声のみを届けることが可能です。Q&A機能を用いての質問受付や、アンケート機能の活用によりスムーズな授業を実現します。また、ノイズキャンセル機能があり周囲の雑音(タイピング音や外部の騒音)を除去してくれます。
なお無償版では60分接続できるため、オンライン授業をLive配信で行う場合にはちょうどよい長さといえるでしょう。ただし、無償版では録画機能を利用できないため、オンデマンド配信の場合は、有料版を利用しましょう。
Google MeetとZoomの違いとは?比較表で特徴を解説
Google Meetの無料版・有料版の詳しい機能の違いついては、「Google MeetとZoomの違いとは?比較表で特徴を解説」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてお読みください。
まとめ
今回は、オンライン授業のやり方について基本から各手法のメリットとデメリット、おすすめツールまで解説しました。授業の目的にあわせてLive配信・オンデマンド配信・ハイブリットを選択し、それぞれに適したWeb会議ツールの活用がポイントです。
おすすめツールで紹介した「Zoom」や「Google Meet」は、無償版と有償版で機能が異なります。
「Zoom」無償版は40分制限でローカルへの録画が可能なため、オンデマンド配信向きです。時間制限が短いためLive配信に活用したい場合は、有償版を検討しましょう。
「Google Meet」無償版は60分制限ですが、録画ができないためLive配信向きです。オンデマンド配信を行いたい場合には、有償版の検討をおすすめします。
これまでのオンライン授業を見直す方も、これからオンライン授業を取り入れる方も、ぜひ本記事の内容を参考にスムーズかつ学習効果の高いオンライン授業を実現してください。