ウェビナーとは?配信のプロが教えるメリットと成功の秘訣
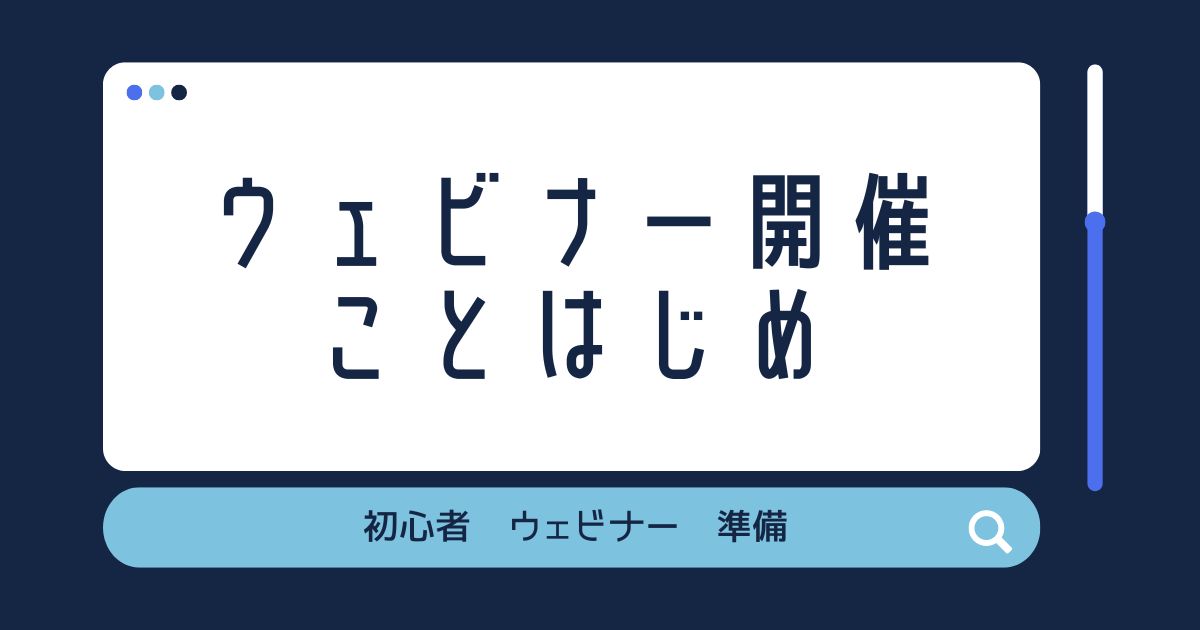
ウェビナーは「Web」と「セミナー」をかけ合わせた造語です。そのまま「Webセミナー」と呼ばれることもあり、コロナ禍で開催する企業が増加しました。株式会社IDEATECHが2023年に実施した調査によると、およそ83%の企業がこれまでに単独でウェビナーを実施したと回答しています。
この記事では、新型コロナ感染症が落ち着き、オフラインに戻りつつある現在でもウェビナーが支持されている理由や開催にあたっての課題を解説しています。また、ウェビナー実施に必要なカメラやマイク等ツールの選び方、自社に合ったウェビナーの開催方法についても紹介していますので参考にしてください。
【無料お役立ち資料】ウェビナー開催ガイド
画像付きでより分かりやすく解説したガイドです。オンラインイベントの開催をご検討されている企業様はぜひダウンロードください。
👉 オンラインセミナー・ウェビナーの企画・運営・サポートについてはこちら
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
ウェビナーとは?
ウェビナーとは、オンライン上で動画・音声を配信するセミナーを指します。
ウェブとセミナーを組み合わせた造語で、「Webセミナー」「オンラインセミナー」とも呼ばれます。
まずはウェビナーがどのような場面で活用できるのか、また、ウェビナーの配信方法について、みていきましょう。
ウェビナーはどんな用途で活用できる?
ウェビナーは、低コスト、場所や時間に制限されない利点から、セミナーや説明会など様々な社外・社内の両方に向けたイベントに活用されています。
セミナーのテーマも幅広く、有識者の基調講演や求職者向けの会社説明会、顧客向けの製品・サービス説明などが代用例です。
オフラインでの開催に比べて低コストで気軽に開催できるため、近年ウェビナーを取り入れる企業は増加傾向となっています。新型コロナウイルスの影響で大人数が集まるリアルのイベント開催が懸念されたことで、ウェビナーへの注目が集まりました。
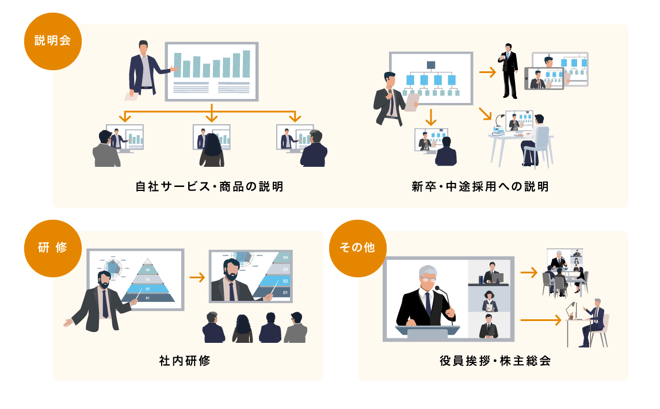
ウェビナーの配信方法
ウェビナーには、「ライブ配信」と「オンデマンド(録画)配信)」の2つのタイプがあります。
ライブ配信
リアルタイムで開催するライブ配信であれば、セミナーの参加者と、チャットやアンケート機能を利用することで双方向にコミュニケーションを取りながら進行することができます。
そのため遠隔でも、「登壇者と対話できる」といった特別感を持たせることが可能です。
また、画面に映る参加者の反応が良ければ内容を深掘りしたり、反対に表情が困っていれば何らかの形で配信内容の補足を加えたりと、必要に応じて配信中でも柔軟にコンテンツを変更することができます。そのため、最新の話題を取り扱いたい場合や、参加者の反応を元に配信内容を調整したい場合には、ライブ配信でのウェビナー開催がおすすめです。
オンデマンド配信
一方の録画配信であれば、事前に作成した動画を何度も配信することができます。
オンデマンド配信の魅力は、参加者が任意のタイミングで視聴可能であるため、ライブ配信では集客できない層にアプローチできることです。
例えば、ライブ配信したセミナーの動画をオンデマンドで配信することも可能です。
また、研修など同じ内容のセミナーを複数回実施する場合、録画配信を行うことでウェビナー主催側のコスト削減に繋がります。
Web会議やオフラインセミナーとの違い
ウェビナーとWeb会議やオフラインセミナーとの違いを見てみましょう。
|
ウェビナー |
Web会議 |
オフラインセミナー |
|
|
開催形態 |
オンライン |
オンライン |
オフライン |
|
コミュニケーション |
テキストのみ |
顔を見ながら |
顔を見ながら |
|
人数 |
大人数 |
少人数 |
会場による |
|
開催コスト |
低い |
低い |
高い |
Web会議とウェビナーの違い
ウェビナーとWeb会議の一番大きな違いは、配信側から参加者の顔が見えるか見えないかです。ウェビナーでもチャットツールや質問機能を使うことで参加者とコミュニケーションを取ることは可能ですが、基本的に参加者がカメラをオンにしてオンライン上に登壇することはありません。
一方でWeb会議は、開催側だけでなく参加側も発言をすることが前提で開催されます。そのため、Web会議の参加人数は多くても数十名で開催されることが一般的です。参加者をさらに少人数に分けるZoomのブレイクアウトルームのような密にコミュニケーションを取れる機能もあります。
ウェビナーは開催側が一方的に発言をするため、参加人数は使用するウェビナーツールの上限までいれることが可能です。その代わり、参加者側から取れるコミュニケーションはチャットツールやアンケート機能などに限られてしまします。
オフラインセミナーとウェビナーの違い
リアルの会場で開催するオフラインセミナーと、オンライン上で実施されるウェビナーにもそれぞれメリット・デメリットがあります。まずオフラインセミナーは、目の前に参加者がいることで、ウェビナーでは見えない参加者の反応やその場の空気感を感じることができ、双方向のコミュニケーションを取ることが容易です。
オフラインセミナーは会場や会場で使用する機材などが必要で、機材の操作や参加者の案内など人件費もかかってきます。ウェビナーなら、オフラインセミナーに比べ会場費や機材費、人件費が削減でき、大きく費用を抑えることが可能です。
またオフラインのセミナーは、参加者の上限が会場の収容人数となります。参加したい人がたくさんいたとしても、収容人数以上の参加希望者がいた場合にはお断りをしなければいけません。一方でウェビナーは、何千人何万人という人に届けることができます。
コロナをきっかけにウェビナーが継続されている理由

ここからは、企業がコロナ禍後もウェビナーを継続する理由について解説していきます。主な理由は、以下の3つです。
理由①:手間や費用を大幅に削減できる
最大の理由は、セミナーの開催にかかる手間や費用を大幅に削減できることです。
今まではセミナーを開催するまでに、会場の選定〜会場の予約〜当日の参加者対応〜撤収作業と、かなりの工数を必要としていました。また、予想される参加人数に合わせて、会場を抑える必要があり、大規模なセミナー開催の場合は、多額の費用がかかっていました。
ウェビナーを活用すれば、会場を抑える必要がないことでレンタル費用の削減が可能です。また、講師(登壇者)が移動する必要もないので、移動交通費やホテル代の削減にも繋がります。参加者にとっても、交通宿泊費が不要な分参加しやすいでしょう。
更に、録画配信の機能によって、同一内容のセミナーを何度も配信できるため、企業側の負担を大きく減らすことができます。
理由②:今までアプローチできなかった層に訴求できる
従来のセミナーでは、会場から近い人しか参加することが困難でした。特に、都市部にオフィスを構える企業では、都市圏の人しか集客ができず、地方からの参加者が少ないという課題がありました。
しかしウェビナーであれば、場所を問わずに多くの参加者を集客することが可能です。地方のみならず、海外からも集客ができるので、新規顧客の開拓に貢献します。
また、会場型のセミナーではどうしても参加人数に制限がありました。大きめの会場を抑えても200〜300人が限度です。ウェビナーは、ツールによって参加できる人数は異なりますが、最大で1,000人規模のセミナーを開催できます。
理由③:質の高いセミナーを実現できる
ウェビナーツールの多くには、アンケート機能やチャット機能が搭載されています。そのため、参加者はセミナーの内容で疑問点が生まれたら、すぐに質問をチャットで送ることができます。セミナーの講師は、対面よりも心理的なハードルが低い状態でコミュニケーションをとることができます。
また、オンデマンドであれば、動画を一時停止したり、繰り返して視聴したりすることで参加者の理解をより深めることができるでしょう。
ウェビナーの課題
コスト削減や新規顧客開拓などメリットのあるウェビナーですが、開催にはいくつかの課題があります。ここではウェビナー開催における課題を3つ紹介します。
課題①:参加者が離脱しやすい
従来の会場で実施されるセミナーと比較すると、ウェビナーは動画感覚で流し見ができてしまうため、参加者が内容に集中しづらいという難点があります。また、会場に赴く必要がなく参加のハードルが低い一方で、退室も簡単できてしまいます。
参加者の離脱を防ぐためには、セミナーの内容に集中してもらえるよう工夫する必要があります。
例えば、セミナー中にアンケートや質問の投げかけを行うなど、参加者が当事者意識を持ってセミナーに参加できる仕組みをつくることが重要です。
課題②:映像・音声が途切れたり、遅延する可能性がある
ウェビナーはオンラインで実施する性質上、開催側・参加側どちらかの通信環境や端末の不良があると途切れたり遅延してしまうおそれがあります。少なくとも開催側は事前に通信環境を確認しておきましょう。
本番中に思わぬトラブルに見舞われないためにも、開催時には有線でのインターネット接続が安心です。
また、専用スタジオでは帯域保証のインターネット契約をしているケースもあります。万全を期した状態でウェビナー開催したい場合は、活用を検討してみるのがおすすめです。
課題③:参加者とコミュニケーションがとりづらい
ウェビナーは、基本的に参加者の顔を見ることなく開催側が一方的に話す形式となります。そのため、参加者とコミュニケーションがとりづらく感じてしまいます。
双方向性のあるコミュニケーションを重視したい場合は、チャットやアンケート機能を上手く活用しましょう。チャットで質問を募りながらセミナーを進めることで、参加者がコミュニケーショに加わるハードルを下げられます。
課題ごとの解決策
ウェビナーを成功させるためには、前述した課題の解決が不可欠です。ここからは課題解決の方法について解説します。
解決策①:離脱を防ぐ配信タイプ・機能があるウェビナーツールを利用する
参加者の離脱を防ぐために配信形式を工夫し、参加者を飽きさせない機能があるツールを選びましょう。
株式会社トップランナーマーケティングの調査によると、参加者の55.9%がウェビナー開始20分以内に視聴継続するか否かを判断。また、約3割が「見るだけ参加」となっており、使用したことがある機能は「チャット」が最多となりました。
詳しい配信タイプについては後述しますが、講演者のみが話す一方向のウェビナーは、長時間になると参加者が飽きる傾向にあります。主催者と参加者がやり取りできるような配信タイプを選ぶのも1つの方法です。
また、チャットやアンケート、挙手機能などを利用して、視聴者が参加できるコンテンツを折り込むと満足感のあるウェビナーを開催できるでしょう。
解決策②:配信に適した機材・スタジオを用意する
ウェビナーを実施する際には、参加者がストレスなく配信を視聴できるように、高品質なマイクやカメラを用意しましょう。防音対策が取られており、機材が充実している外部の専用スタジオを利用するのもおすすめです。
デバイスにあらかじめ搭載されている内蔵マイクやカメラでもウェビナーは開催できますが、機能性の低さは否めません。回線や機材のトラブルは致命的といえるため、事前に本番同様のリハーサルを行い、通信や機器に問題がないか確認しておきましょう。
通信環境が不安定な場合はサブのインフラ環境を準備しておくと安心です。
解決策③:ハイブリッド開催をする
コミュニケーションの取りづらさを解決するために「ハイブリッド開催」を検討してみましょう。ハイブリッドとは、オンラインとオフラインのセミナーを同時に開催する配信形態です。
ハイブリッド開催では、通常のセミナーと同じように会場の予約や設営が必要となるためコスト削減のメリットはなくなりますが、参加者と直接交流を図れるという強みがあります。
会場で参加している観客の反応をそのまま配信できることで、臨場感を演出できる点もメリットです。遠方やスケジュールの都合が合わない人はオンラインによる参加が可能なため、参加のハードルを下げられてより多くの視聴者に発信ができます。
ウェビナーツールの選定ポイント
ウェビナーツールにはさまざまなサービスがあります。それぞれの特色を把握した上で、目的に合ったツールを選びましょう。
ここでは、ウェビナーツールを選定する際のポイントを予算、機能、サポートの3つの観点から解説します。
予算
ウェビナーツールの料金は大きく分けて、「従量課金型」と「サブスクリプション型」の2種類あります。「従量課金型」は1回きりの契約でその都度料金が発生し、「サブスクリプション型」は契約期間中であれば同一料金で何度も利用できます。
ウェビナーを高頻度で実施する場合は「サブスクリプション型」、頻度が高くない場合は「従量課金型」というように、ウェビナーの実施頻度によって利用するサービスを使い分けましょう。
また、ウェビナーを実施する目的に合わせてツールにかける予算を決めるのもポイントです。例えば、リード獲得目的のウェビナーの場合、リード獲得単価の数字が予算の参考になります。
配信形態・タイプ
ウェビナーには前述した「ハイブリッド配信」のほかに、「ライブ配信」や「オンデマンド配信」といった配信形態が主流です。また、配信タイプも3種類あり、コミュニケーションの取り方が異なります。
オンデマンド・ライブ
あらかじめ録画した動画を配信するオンデマンド配信なら、録画機能やアーカイブ保存機能があるツールを選ぶとよいでしょう。撮り直しや編集ができ、録画した動画は繰り返し配信できます。
ただし、双方向のコミュニケーションは取れず、視聴者の反応をリアルタイムで見ることはできません。
生中継によるライブ配信では、最大参加人数や配信時間、コミニュケーション機能の有無などが重要になります。とくに大規模イベントを開催する場合は、最大参加人数に制限がないツールを選ぶと安心です。
また、チャットやコメントなどのコミュニケーション機能を活用すれば、視聴者の意見や反応をリアルタイムに確認できるためオフラインセミナーに近い形式で開催できます。質疑応答も可能で、視聴者にとっては疑問を解消しやすいウェビナーになるでしょう。
配信タイプ(1対N型・N対N型・テーブル型)
配信タイプには「1対N型」「N対N型」「テーブル型」の3種類があります。以下はそれぞれのコミュニケーションの違いと特徴をまとめたものです。
|
配信タイプ |
特徴 |
|
1対N型 |
・主催者が1名もしくは1社で、大勢の参加者に向けて配信する形式。 ・コミュニケーションは一方向 ・講演会やセミナー向き |
|
N対N型 |
・主催者と参加者が双方にやり取りをしながら配信する形式。 ・双方向のコミュニケーションが可能 ・大人数による開催には不向きのためWeb会議におすすめ |
|
テーブル型 |
・バーチャルなテーブル上で参加者同士が講義やディスカッションする形式。 ・テーブル単位であれば大人数の実施も可能 ・オンラインイベント向き |
参加したくなる機能があるかどうか
配信方法やウェビナー中に必要な機能によってツールの選び方も異なります。主にチェックしたい機能を3つ紹介しましょう。
チャット・スタンプ機能
ウェビナーツールのコミュニケーションには、チャットやスタンプといった機能が備えられています。
チャット機能とは、主催者と参加者が文字でコミュニケーションを取るための機能です。マイクを使用しなくても質問や意見を送ることができます。また、ファイルやURLの送信にも活用できるため、ウェビナー進行に役立つ機能といえるでしょう。
スタンプは、絵文字やリアクションを使って意思表示を行う機能です。「発言しづらい」「メッセージを送りづらい」といった際に気軽に意思表示ができる点がメリットです。
画面レイアウト
多くのウェビナーツールでは、必要に応じて画面レイアウトを変更できます。例えば、ファイルを共有する場合「ファイルをメインで表示させて参加者をサムネイルで表示する」、あるいは「ファイルをメインで表示させて発言者のみ表示する」といったレイアウトが可能です。
ウェビナー中に参加者全員を表示するか、発言者のみを大きく表示するかといった選択もできます。ウェビナーのプログラムや開催規模、配信方法によっても大きく異なりますので、まずはどのようなウェビナーを開催したいかを設定しましょう。
質疑応答
コミュニケーションの取りづらさを解消するために質疑応答機能も有効です。質疑応答機能とは、ウェビナー中に質問や回答ができるコミュニケーション機能。質問や回答は主催者だけでなく参加者も閲覧できるため、より満足度の高いウェビナー開催を実現できます。
前述したチャット機能と似ていますが、匿名質問ができたりメッセージがスレッドで表示できたりと、より質疑応答に特化しているのが異なる点です。
サポート
手厚いサポートが受けられるサービスを選ぶというのも、ツールを選ぶ際の重要なポイントです。
配信のサポートや専用スタジオの貸出をしているサービスを選べば、手軽に高品質なウェビナーを配信できます。
タイプ別ウェビナーツール比較
ここからはウェビナーツールを「1対N型」「N対N型」「テーブル型」の3タイプ別に紹介します。
1対N型
|
V-CUBE セミナー |
Zoom ウェビナー |
YouTube Live |
|
|
開催時間制限 |
40分 |
なし |
無制限 |
|
最大参加人数 |
最大26,000拠点 |
1万人 |
無制限 |
|
視聴ログ分析 |
レポート作成可能 |
ウェビナーレポートの作成が可能 |
アナリティクスのみ (YouTube Studio) |
|
アーカイブ保存 |
無制限に保存可能 |
ローカル保存・クラウド保存可能 |
無制限に保存可能 |
|
チャットの有無 |
あり |
あり |
あり |
|
参加方法 |
URL共有 |
URL共有 |
URL共有 |
VCUBEセミナー

・対象企業:個人〜大企業まで幅広く利用可能
・価格:公式HPからお問い合わせください。
「V-CUBEセミナー」は、Web会議のクラウド市場で13年連続シェアNo.1を誇るウェビナーの代表的なツールです。ライブ配信とオンデマンド配信の双方に対応。最大で10,000拠点に配信できることから、大規模なウェビナーを開催できます。
受講者の声を集める「アンケート機能」や講師と受講者のコミュニケーションを促す「チャット機能」が搭載されている他、資料を大きく見せることができる資料共有の機能も備えています。
また、視聴者側にも便利な機能が多くあるのも魅力です。マルチデバイスからの参加や資料と講師画面の切り替えが可能です。タイムシフト再生が可能なことから、途中で参加しても過去の動画をその場で追うことができます。
Zoom ウェビナー
Zoom ウェビナーは、Zoomが提供するサービスで、Zoomの有料プランを契約して利用できる機能です。各国で利用されており、通信速度が低速でも途切れにくいのが特徴です。
最大10,000人まで参加でき、チャットやQ&A機能でコミュニケーションを取ることができます。主催者であるホストと、登壇者であるパネリストをわけて設定し、参加者はビデオや音声は共有せず、視聴者として参加します。
開催時間制限:なし
最大参加人数:1万人
最大主催者:ホストは1人(共同ホストに制限なし)
視聴ログ分析:ウェビナーレポートの作成が可能
アーカイブ保存:ローカル保存・クラウド保存可能
チャット:あり
参加方法:URL共有
YouTube Live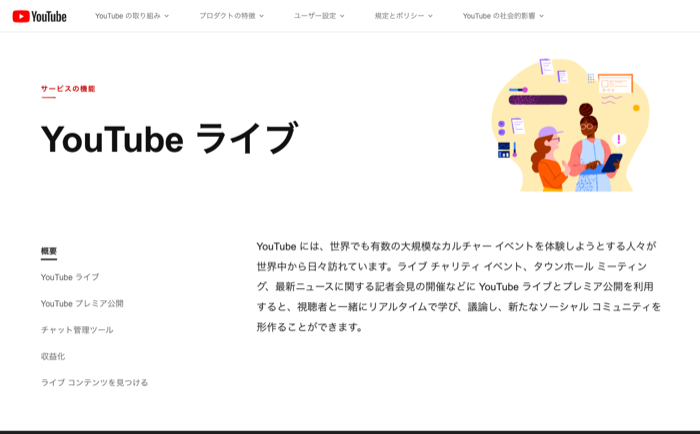
YouTube Liveは、動画配信サービスYouTubeを利用したライブ配信サービスです。
誰でもURLから視聴でき、参加人数に制限はありません。ライブ配信のみの公開、もしくはライブ配信後のアーカイブ公開の選択が可能です。
開催時間制限:無制限
最大参加人数:無制限
視聴ログ分析:アナリティクスのみ(YouTube Studio)
アーカイブ保存:無制限に保存可能
チャット:あり
参加方法:URL共有
N対N型
|
Zoom ミーティング |
Google Meet |
Skype |
|
|
開催時間制限 |
40分(3人以上) |
24時間 |
24時間 |
|
最大参加人数 |
最大1000人 |
100人 |
100人 |
|
視聴ログ分析 |
なし |
なし |
なし |
|
アーカイブ保存 |
ローカル保存可能 |
不可 |
30日間ローカル保存、ダウンロード可 |
|
チャットの有無 |
あり |
あり |
あり |
|
参加方法 |
URL共有 |
URL共有 |
URL共有 |
Zoom ミーティング
Zoom ミーティングとは、Web会議サービスZoomが提供するサービスです。
無料プランでは、最大100人まで参加できますが、開催時間が40分と短いのが欠点です。ただ、世界各国で利用されており、通信速度が低速でも途切れにくいのが特徴です。
開催時間制限:40分(3人以上)
最大参加人数:100人
視聴ログ分析:なし
アーカイブ保存:ローカル保存可能
チャット:あり
参加方法:URL共有
登録はこちら
Google Meet
出典:Google Meet(旧称 Hangouts Meet) - 無料のビデオ会議
Google Meetは、もともと「Hanguots Meet」と呼ばれていた、Googleが提供するビデオ会議システムです。
デバイスを問わず簡単に参加できるのが特徴です。ウェビナーとして利用する場合は、参加者がミュートを外さないよう、画面共有をしないように案内が必要です。
開催時間制限:24時間
最大参加人数:最大1000人
視聴ログ分析:なし
アーカイブ保存:不可
チャット:あり
参加方法:URL共有
Skype
出典:Skype | 無料通話とチャット用のコミュニケーション ツール
Skypeは、Microsoftが提供するビデオ通話サービスです。画面共有やグループでの会議も可能です。
サインアップやダウンロードも不要で、URLを共有するだけですぐに参加できます。
開催時間制限:24時間
最大参加人数:100人
視聴ログ分析:なし
アーカイブ保存:30日間ローカル保存、ダウンロード可
チャット:あり
参加方法:URL共有
テーブル型
|
EventIn |
Remo |
|
|
最大参加人数 |
5,000人(300ブース表示可能) |
50人 |
|
視聴ログ分析 |
あり |
なし |
|
アーカイブ保存 |
可能 |
HD録画、ストレージ40時間 |
|
チャットの有無 |
あり |
あり |
|
参加方法 |
URL共有 |
URL共有 |
EventIn
EventInは、ブイキューブが提供する、オンラインイベントプラットフォームです。
参加者は、イベントに簡単に登録でき、セッションを視聴やWeb上でのブース間の移動、商談までを行えます。出展者は、自分のブースのアピール、ブース訪問者へのプレゼンテーションや、動画・資料の展示などから、商談に繋げることが可能です。
Remo
出典:Remo Conference - リモートイベントツール
Remoは、「よりリアルに近いオンラインイベントを」をコンセプトにした、オンライン交流ツールです。
テーブルを移動しながら参加者間で会話ができるのが特徴で、ネットワーキング、カンファレンス、展示会などのセッションを同時に開催し、参加者は自由に移動しながら参加できます。
無料トライアルは14日間限定です。
開催時間制限:5時間
最大参加人数:50人
視聴ログ分析:なし
アーカイブ保存:HD録画、ストレージ40時間
チャット:あり
参加方法:URL共有
ウェビナーツール比較7選。自社に合ったツール選定のポイントは?
有料ウェビナーツールは「ウェビナーツール比較7選。自社に合ったツール選定のポイントは?」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
安心な配信を実現させる機材・サービス
ウェビナーを行う際には、セミナー参加者がストレスなく配信を視聴できる事が重要です。
ノートPCに内蔵のカメラやマイクでも開催は可能ですが、専用の製品を利用することでより品質の高い映像・音声を提供することができ、視聴者の満足度や理解度を高めることができます。
ウェビナー用のカメラ
近年市販されているノートPCやタブレットのほとんどには、カメラが内蔵されています。
通常のWeb会議であれば、内蔵カメラの画角・画質で事足りるでしょう。ある程度画質が低くても、カメラとの距離が近いため表情を読み取るには十分で、問題なくコミュニケーションが可能です。
しかし、ウェビナーにおいては、
- 画角がせまい
- ズームができない
- 解像度が低い
- カメラの位置を動かしづらい
という理由から内蔵カメラはあまりおすすめできません。
外部カメラなら映像の乱れも少なく、画面構成や光の調整などが容易なため、よりバリエーション豊かな演出が可能です。高画質であることから資料の文字も鮮明に見えます。
必要に応じて外付けのWebカメラを用意すると良いでしょう。
ウェビナー配信成功の鍵はカメラにあり!失敗しないカメラ選びのコツとおすすめ4選
ウェビナー用のカメラは「ウェビナー配信成功の鍵はカメラにあり!失敗しないカメラ選びのコツとおすすめ4選」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
ウェビナー用のマイク
マイクも一般的なノートPCやタブレットに内蔵されており、イヤホンにもマイクが内蔵されているものがあります。
それらのマイクでウェビナーを開催することは可能ですが、機種によっては聞こえづらかったり、ノイズ・雑音が入る場合もあるので、やはりウェビナーには外付けマイクを用意したほうがベターであることは間違いありません。
マイクを選ぶ際のポイント
ウェビナーに向けて外付けマイクを新たに用意する場合には、以下のポイントに考慮しましょう。
- 指向性:「単一指向性」or「無指向性」
- 接続方式
- ウェビナーの登壇人数
おすすめのウェビナー用マイク6選|製品選びのポイントとは?
ウェビナー用のマイクは「おすすめのウェビナー用マイク6選|製品選びのポイントとは?」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
ウェビナー用スタジオ
インターネット環境さえあれば誰でも開催できるウェビナーですが、
- ウェビナーを開催できる場所がない
- ウェビナーを配信するための設備がない
- そもそもウェビナーをどのように実施すればいいのかわからない
などの悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった場合にはウェビナー用のスタジオの利用すると良いでしょう。
多くのウェビナー用のスタジオは配信に必要な機材を有しており、複数台のカメラでの撮影や合成などの高度な配信を実現することも可能です。
ウェビナーに最適なスタジオ3選!場所の確保から配信までサポート
ウェビナー用のスタジオは「ウェビナーに最適なスタジオ3選!場所の確保から配信までサポート」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
ウェビナー代行サービス
より手軽にウェビナーを配信したい場合や、失敗できない重要なウェビナーを配信する場合は、準備から当日の配信まで代行してくれるウェビナー代行サービスを利用すると良いでしょう。
ウェビナー代行サービスを利用すれば、配信トラブルへの不安を抱えることなく、人員・負担を減らしながら高クオリティのウェビナーを開催することができます。
また、コンサルティングを行うウェビナー代行もあるため、自社のウェビナーの開催目的や得たい効果を目指して、より効果的なウェビナーを実現できるようになるでしょう。
👉 オンラインセミナー・ウェビナーの企画・運営・サポートについてはこちら
【事例あり】ウェビナー代行サービスとは?メリット・デメリット、選定ポイントを解説
ウェビナー用のスタジオは「【事例あり】ウェビナー代行サービスとは?メリット・デメリット、選定ポイントを解説」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
ウェビナーを成功に導く6つの注意点と対策
ここからはウェビナーを成功に導くための、以下の6つの注意点と対策を紹介します。
- ターゲットを明確化し、ターゲットの課題に沿ったテーマを設定する
- 参加メリットを明確にする
- スムーズに参加できるようにする
- セミナー開演前から映像・音声を配信をすることで、受講者環境チェックを!
- ウォーミングアップで、LIVEセミナーならではの機能を体験してもらう
- アンケートを取る場合は「資料化」&「セミナー中」に実施
1.ターゲットを明確化し、ターゲットの課題に沿ったテーマを設定する
大前提としてまず最初に、ウェビナーの「集客したいターゲット」を明確にしましょう。
集客したいターゲットを明確にするには、そもそもウェビナーを開催する目的に立ち返って設計することがおすすめです。
ウェビナー開催の目的が「新規リード獲得」か「リードの育成」かによって、開催するウェビナーのテーマや集客方法も異なります。
新規リード獲得であれば、より多くの新規顧客にリーチするような集客手段を取ります。リードの育成であれば、すでに保持しているリードに対してアプローチできる集客手段を取ります。
ウェビナー開催の目的・ターゲットを明確にしたうえで、ターゲットが抱える課題を解決できるようなテーマを設定して集客を効果的にしましょう。
2.参加メリットを明確にする
ウェビナーへの参加メリットを明確にしましょう。
参加を検討しているユーザーは、勉強熱心で効率よく情報収集したいと考えているため、参加したことで得られる情報が事前に分かると参加を決めやすくなります。自社ウェビナーならではの参加メリットを打ち出しましょう。
ほかにも、「アーカイブ動画を視聴できる」「セミナーで使用した資料をダウンロードできる」「直接講師に質問できる」「特別な割引がある」などといった参加メリットをつけましょう。
こうしたメリットをウェビナーのイベントページに目立つように掲載し、より魅力的に見せるのがポイントです。
3.スムーズに参加できるようにする
参加者がスムーズにウェビナーに参加できるようにすることも、集客するうえでのポイントです。
ウェビナー参加でつまづく箇所として、「参加申し込み」と「ウェビナーへの入室」が挙げられます。
参加申し込みにあたり、申し込みフォームの項目が多すぎると参加ハードルが上がり、離脱が増えてしまいます。申し込みフォームの項目は、基本的には以下のような基本情報に留めることをおすすめします。
- 氏名
- 会社名
- 電話番号
- メールアドレス
- 質問(自由記述)
また、ウェビナーへの入室方法が分からず参加できない、といったことがないように準備しておくことも重要です。せっかく申し込んだのに参加できないと、ウェビナーや主催企業への印象が下がってしまいます。
申込者へのリマインドメールに、参加方法を詳しく載せて案内するなどして、スムーズに参加できるようにしましょう。
4.セミナー開演前から映像・音声を配信しておく
オンラインセミナーの開場時間は、開始時刻の15分前から30分前に設定し、その間は何かしらの音と映像を流しておきましょう。
この目的は、その時間に受講者に音と映像がきちんと見れるかを確認してもらい、トラブルがあれば対処してもらうためです。
トラブルがある場合は、再入場してもらうかネット回線を確認してもらう必要があります。ただ、これには少し時間がかかってしまうので、セミナー開始前にチェックしてもらうことで、開始早々の音声トラブルやネットトラブルを回避することができます。
5.ウォーミングアップで、LIVEセミナーならではの機能を体験してもらう
LIVEセミナーの効果を上げるためには、いかに機能を使いこなし、受講者のエンゲージメントを高めるかが重要になってきます。
セミナー開始直後にチャットや質問機能をウォーミングアップとして使用してもらい、「使い方を覚える」&「入力への心理的ハードルを下げる」時間を必ず設けましょう。
ウォーミングアップ質問の内容は「今日の朝ご飯」「参加地」「セミナーで聞きたいこと」など、簡単な質問を投げかけることが重要です。
そして始めだけではなく、15分に一度程度チャット機能を使う機会を設けましょう。そうすることで、参加者の集中力を保ち、一方的なセミナーになることを防げます。
このように、配信ツールの機能を主催者だけでなく参加者も使いこなせる環境を作ることが、セミナー全体の満足度向上の鍵となります。
6.アンケートを取る場合は「セミナー中に」
理解度や満足度を測るアンケートを取る場合は、後日改めてメールを送信するのではなく、セミナー中に資料などを提示しながら実施するのがポイントです。セミナー中に行うことで回答率は非常に高くなります。
また、「セミナーはいかがでしたか」「講師はどうでしたか」といった抽象的な質問には回答しにくいものです。回答の方向性にもばらつきが出てしまい、期待しなかった方向性の回答は後の集計や分析の妨げとなるでしょう。
そのような事態を避けるためにも、「セミナーの内容はあなたの知りたいことでしたか」「講師の説明のわかりやすさは10点満点中何点でしたか」というような具体的な聞き方を意識して、迷わず回答できるように配慮しましょう。
そうすることで、作成者の意図に沿った回答が得られ、集計や分析もしやすくなります。
ウェビナー開催のための完全ガイド!年間5,000配信のプロが実践する事前準備と運営ポイントとは?
ウェビナーの開催方法は「ウェビナー開催のための完全ガイド!年間5,000配信のプロが実践する事前準備と運営ポイントとは?」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
まとめ|ウェビナーの効果を最大化しよう
本記事では、ウェビナーの概要やコロナ禍以降も支持される理由と課題、メリット、そしてウェビナーを成功させるための注意点について紹介してきました。
ウェビナーは、オフラインでの開催よりも低コストで工数をかけずにセミナーを開催できるため、企業の生産性向上にも寄与します。
また、これまでターゲットになり得なかった、地方都市や海外に住む人を取り込むことも可能です。
移動のための時間や交通費がかからないウェビナーは、まさに主催者・参加者双方にとってwin-winであるといえるでしょう。





